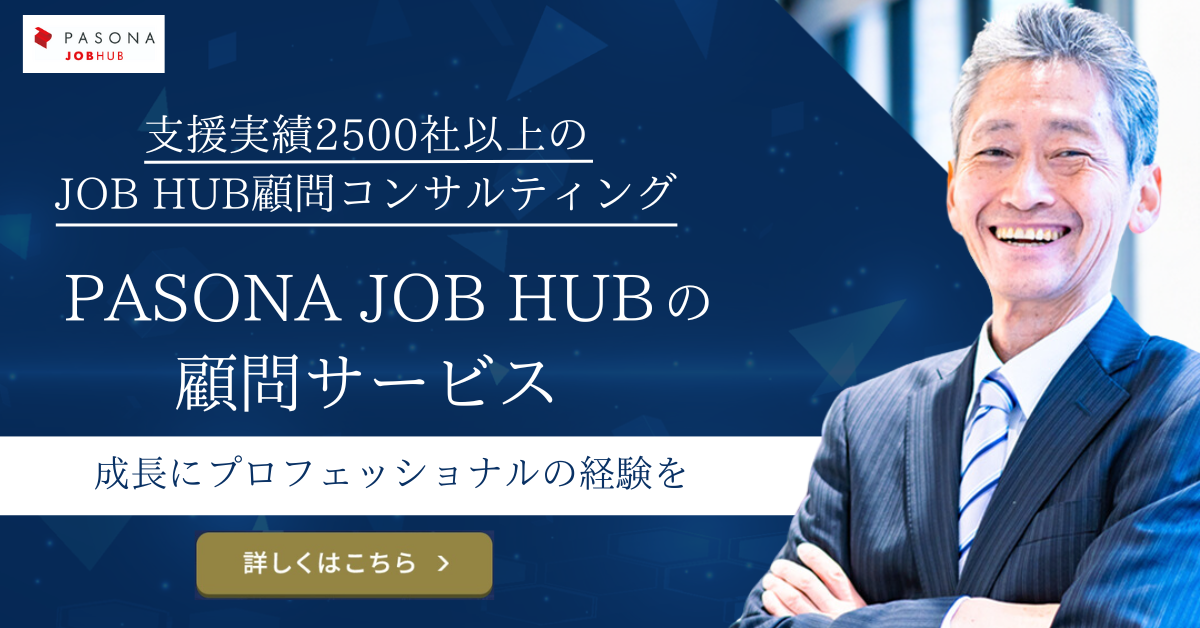企業経営において、障がい者雇用は無視できない重要な課題となっています。法定雇用率の段階的な引き上げや、社会的責任の観点からも注目される中、「どのように障がい者雇用に取り組むべきか」「どんなメリットがあるのか」と悩む事業責任者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障がい者雇用の基礎知識から具体的な進め方、企業が得られるメリット、活用できる支援制度まで、事業責任者として知っておくべき情報を網羅的に解説します。これから障がい者雇用に取り組む企業はもちろん、すでに取り組んでいるがさらに効果的な施策を検討したい企業にとっても、有益な情報となるでしょう。
目次
障がい者雇用促進法とは
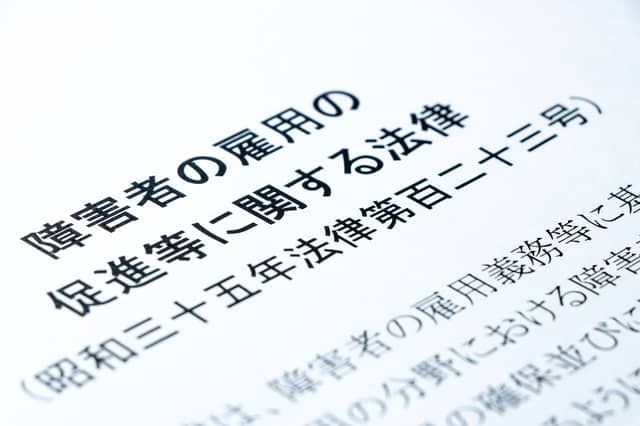
障がい者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)は、障がいのある人の職業の安定を目的として制定された法律です。
令和4年には一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和5年から順次施行されました(※厚生労働省「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」より)。
企業に求められているのは、形式的な対応だけではなく、その人が安定して働けるためにどのような支援や配慮が必要かを丁寧に検討することです。
▼障がい者雇用の採用面や制度面の課題を、お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム┃ProShare(プロシェア)
障がい者雇用で企業がやらなければならないこと

障がい者雇用を進めるにあたり、企業には法律に基づいたいくつかの義務があります。最も基本的なのが、常用労働者数に応じた「法定雇用率」の達成です。
令和7年現在、民間企業の法定雇用率は2.5%と定められており、これは40人以上の従業員を雇用する企業には、少なくとも1人以上の障がい者を雇用する義務があることを意味します(40人×2.5%=1人)。この比率は段階的に引き上げられ、令和8年7月からは2.7%に引き上げられる予定です(※厚生労働省「障害者雇用率制度」より)。
また、企業には以下のような義務も課せられています。
<雇用状況の報告義務>
毎年6月1日時点の障がい者の雇用状況をハローワークに報告(障害者雇用促進法43条第7項)
<差別の禁止>
障がいを理由とした募集・採用・待遇等における差別的取扱いの禁止(障害者雇用促進法第34~35条)
<合理的配慮の提供>
障がいのある人が能力を発揮できるよう、業務や職場環境における配慮を行うこと(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)
こうした制度は、企業が障がい者の職場参加を確保するために設けられています。
合理的配慮の例
企業が実施すべき合理的配慮の例としては、以下のようなものが挙げられます。
| 募集・採用時 |
|
| 採用後 |
|
参照元:周知用リーフレット
合理的配慮は障がいのある人一人ひとりに合わせて提供されるべきものです。従って、どのような措置をとるかについては、障がいのある人と事業主とでよく話し合った上で、企業にとって過度な負担にならない範囲で、実施していく姿勢が求められます。
障がい者雇用の手順
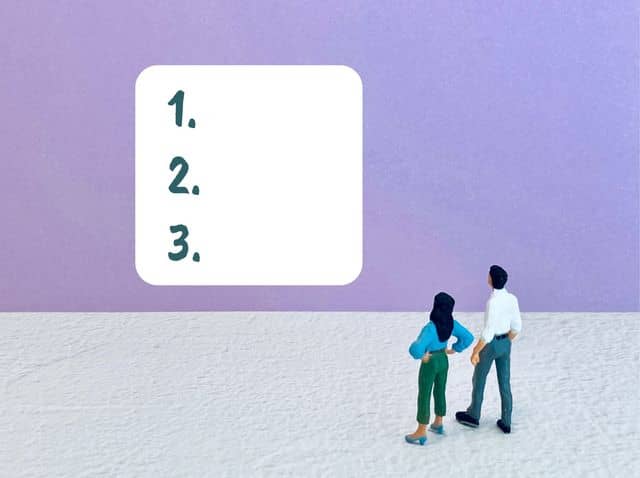
障がい者雇用を成功させるためには、計画的かつ段階的に準備を進めることが重要です。募集から採用、そしてその後の定着支援まで、一連の流れを理解し、それぞれのステップで適切な対応を行うことが求められます。
【ステップ1:障がい者雇用への理解を深める】
まず、人事担当者だけでなく、経営層や受け入れ部署の従業員も含めて、障がい者雇用に関する正しい知識と理解を深めることがスタートラインとなります。ハローワークが実施する事業主向けのセミナーに参加したり、専門機関から情報提供を受けたりするのも有効でしょう。
【ステップ2:受け入れ準備と業務の切り出し】
次に、社内で障がいのある人を受け入れるための体制を整えます。具体的には、任せる業務を検討する「業務の切り出し」を行います。いきなり複雑な業務を任せるのではなく、既存の業務を細分化し、障がいのある人の特性や能力に合わせて担当できる作業を特定。また、必要に応じて作業スペースの整備や支援機器の導入も検討しましょう。
【ステップ3:募集・採用活動】
担当してもらう業務が決まったら、求人活動を開始します。ハローワークの専門窓口に求人を申し込むのが一般的ですが、民間の障がい者専門の求人サイトや人材紹介サービスを活用する方法もあります。選考においては、障がいの特性を理解した上で、応募者の能力や適性を見極めることが重要です。面接時には、合理的配慮としてどのような支援が必要かを確認し、入社後のミスマッチを防ぐよう努めます。
【ステップ4:受け入れと職場定着支援】
採用が決まったら、スムーズに職場に馴染めるよう、受け入れ部署の従業員への事前説明や、入社後のサポート体制を整えます。特に、入社初期は環境の変化や業務への適応に不安を感じやすいため、定期的な面談や相談しやすい雰囲気づくりが大切です。また、地域障害者職業センターのジョブコーチ支援などを活用し、専門的なサポートを受けながら職場定着を図ることも有効な手段となります。障がいのある人が安心して長く働き続けられるよう、継続的なフォローアップが求められます。
障がい者雇用の現状

日本における障がい者雇用は着実に進展しています。厚生労働省が発表した「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業に雇用されている障がい者数は67万7,461.5人で、前年比5.5%増と過去最高を記録しました。実雇用率も2.41%と13年連続で上昇しています。(※参考①)
【法定雇用率の推移】
民間企業の法定雇用率は次のような推移になっています。
- 平成11年(1999年)~平成24年(2012年)まで:1.8%
- 平成25年(2013年)〜平成29年(2017年):2.0%
- 平成30年(2018年)〜令和2年(2020年):2.2%
- 令和3年(2021年)〜令和5年(2023年):2.3%
- 令和6年(2024年)~令和8年(2025年)6月:2.5%
- 令和8年(2026年)7月~:2.7%
このように、障がい者雇用の促進に向けて法定雇用率は段階的に引き上げられており、企業には長期的な視点での対応が求められています。(※参考①)
【業種別の雇用状況】
業種によって障がい者雇用の状況には差があり、たとえば医療・福祉業界では実雇用率が比較的高い一方、情報通信業などでは実雇用率が低くなっています。(※参考①)
そこで障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する「除外率制度」が設けられていました。
しかしこの除外率制度はノーマライゼーションの観点や職場環境の整備が進んでいることなどから、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。
実際に、令和6年度の報告時に除外率が5%または10%の業種については、令和7年度からは除外率制度の対象外となっており、今後より一層の障がい者雇用の促進が求められています。(※参考②)
障がい者雇用の課題

障がい者雇用が促進される一方で、多くの企業が様々な課題に直面しています。
主な課題としては以下が挙げられます。
- 業務内容とのミスマッチ
採用時に期待された業務と、実際に障がいのある人が持つスキルや特性との間にミスマッチが生じることがあります。
たとえば、コミュニケーションが重視される業務に、対人関係に困難を抱える人を配置してしまったり、細かな作業が苦手な人に精密さを求められる業務を任せてしまったりするケースです。
これは、採用前の業務内容の明確化や、本人の適性・希望の十分なヒアリングが不足している場合に起こりやすいと言えます。
- 定着率の低さ
障がい者雇用における課題の一つに、職場への定着率が低い傾向がある点が挙げられます。
その背景には、職場環境への適応の難しさ、人間関係の悩み、体調管理の困難さ、キャリアアップへの不安など、さまざまな要因が考えられます。
特に、入社後のフォローアップ体制が不十分であったり、周囲の理解やサポートが得られにくかったりすると、早期離職につながるリスクが高まります。
- 受け入れ体制や教育制度の課題
社内の受け入れ体制が十分に整っていないことも、障がい者雇用を難しくする要因です。
たとえば、障がいのある人への指示の出し方やコミュニケーション方法について、現場の従業員が戸惑ってしまうケースがあります。また、障がいの特性に合わせた研修制度やキャリアパスが整備されていない企業も少なくありません。 これらは、障がいのある人が能力を発揮し、長期的に活躍していく上での大きな障壁となる可能性があります。
これらの課題を乗り越え、障がい者雇用を成功に導くためには、企業側の積極的な取り組みが不可欠です。そして、これらの課題解決は、企業にとって新たなメリットを生み出す可能性も秘めています。
障がい者を雇用するメリット
障がい者雇用は、法律で定められた義務であると同時に、企業にとって多くの価値をもたらす機会でもあります。法定雇用率の達成や社会貢献といった側面だけでなく、事業責任者の視点からも見逃せない具体的なメリットが存在します。
障がい者を雇用することで企業が得られる主なメリットは以下の通りです。
- 企業価値・イメージの向上
- 助成金や優遇措置の活用
- 組織の多様性によるイノベーション
- 従業員の意識改革と職場の活性化
- 人手不足の解消につながる
これらのメリットについて、それぞれ詳しく解説していきましょう。
1. 企業価値・イメージの向上
障がい者雇用への積極的な取り組みは、企業の社会的評価を高める要因となります。ダイバーシティ&インクルージョンを推進する企業として認知されることは、現代社会において非常に重要な意味を持ちます。多様な人材が活躍できる職場環境を整備することは、SDGs(持続可能な開発目標)の「8. 働きがいも経済成長も」や「10. 人や国の不平等をなくそう」といった目標達成にも直接的に貢献するものです。
このような社会貢献活動は、顧客や取引先からの信頼獲得につながるだけでなく、投資家からの評価向上も期待できます。ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)が拡大する中で、社会的責任(CSR)を積極的に果たす企業は、長期的な成長が見込める投資対象として注目される傾向にあります。さらに、メディアに取り上げられる機会が増えれば、企業ブランドの認知度向上や、優秀な人材の採用においても有利に働く可能性があります。
2. 助成金や優遇措置の活用
障がい者を雇用する企業は、国や地方自治体からさまざまな助成金や優遇措置を受けることができます。これらは、障がい者雇用にかかる経済的な負担を軽減し、より積極的な取り組みを後押しすることを目的としています。
代表的なものとして、「特定求職者雇用開発助成金」があります。これは、ハローワークなどの紹介により、障がい者等の就職困難者を継続して雇用する事業主に対して支給されるものです。また、「トライアル雇用助成金」も、企業にとって雇用のミスマッチを防ぐ上で有効な制度です。
さらに常時雇用している労働者数が100人を超える企業は、法定雇用率を達成できない場合、障害者雇用納付金の支払い義務が発生しますが、反対に、法定雇用率を達成している企業には、調整金・報奨金が支給されます。
このように、助成金や優遇措置をうまく活用することで、障がい者雇用のための環境整備や人材育成にかかるコストを抑えつつ、安定的な雇用を実現することが可能になります。
3. 組織の多様性によるイノベーション
障がいのある人を組織に迎え入れることは、企業内に新たな視点や多様な経験をもたらし、イノベーション創出のきっかけとなり得ます。多様なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、固定観念にとらわれない自由な発想が生まれやすくなり、新しい商品やサービスの開発、業務プロセスの改善などにつながる可能性が高まります。
また、障がいのある人が働きやすい環境を整備する過程で、業務の見直しや効率化が進むことも少なくありません。たとえば、誰にでも分かりやすいマニュアルを作成したり、コミュニケーション方法を工夫したりする取り組みは、結果として組織全体の生産性向上に貢献する場合があります。多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる組織は、変化の激しい現代社会において、持続的な成長を遂げるための重要な基盤となるでしょう。
4. 従業員の意識改革と職場の活性化
障がいのある人とともに働く経験は、他の従業員にとっても多くの気づきや学びをもたらし、職場全体の意識改革を促します。日常的に接することで、障がいに対する理解が深まり、これまで漠然と抱いていた偏見や固定観念が解消されることも少なくありません。
その結果、従業員一人ひとりの間に、相手の立場を尊重し、思いやりを持って接する意識が自然と育まれていきます。コミュニケーションの取り方にも工夫が生まれ、互いに協力し合う雰囲気が醸成されることで、職場全体の風通しが良くなる傾向があります。このようなポジティブな変化は、従業員のモチベーション向上やチームワークの強化につながり、ひいては組織全体の活性化と生産性の向上にも貢献すると期待できるでしょう。
5. 人手不足の解消につながる
少子高齢化に伴う労働力人口の減少が深刻化する中で、障がい者雇用は企業にとって貴重な人材確保の手段の一つとなり得ます。
企業が障がいのある人の能力や特性を正しく理解し、適切な業務の切り出しや職場環境の整備を行うことで、これまで潜在的な労働力とされてきた人材の活用が可能になります。
障がい者雇用は、単なる社会貢献に留まらず、企業の持続的な成長を支える重要な戦略の一つと捉えることができます。
障がい者を雇用しないデメリット
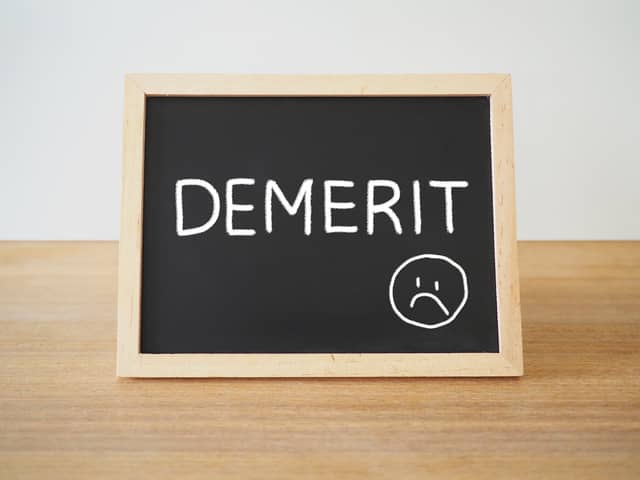
障がい者雇用は、企業にとって多くのメリットをもたらす一方で、これを怠った場合にはいくつかのデメリットやリスクが生じる可能性があります。法律で定められた義務を遵守しないことによる直接的な影響だけでなく、社会的な評価や組織運営の観点からもマイナスの影響を受けることが考えられます。
企業が障がい者を雇用しない場合に考慮すべき主なデメリットは以下の通りです。
- 障害者雇用納付金の負担
- 助成金を受けられない
- 法令違反リスクと企業イメージの低下
- 多様性を欠いた組織の硬直化
- 採用競争力への悪影響
これらのデメリットについて、次項からそれぞれ詳しく解説していきます。
1. 障害者雇用納付金の負担
法定雇用率を満たせなかった場合、不足している障がい者1人あたり月額50,000円(令和6年5月現在)の納付金を支払う義務が発生します(※対象は常用労働者100人を超える企業)。
たとえば…
- 法定雇用障害者数:5人
- 実際の雇用数:3人(不足2人)
- 月額納付金:50,000円 × 2人 = 100,000円
- 年間負担額:1,200,000円
このように、人数が少なく見えても、年間で見れば百万円単位の損失につながる可能性があります。単なる「罰金」としてではなく、計画的に雇用を進めることで、無駄な出費を回避できる制度だといえます。
2. 助成金を受けられない
国は、障がい者雇用を積極的に進める企業を支援するために、さまざまな助成金制度を設けています。これには、障がい者を新たに雇い入れた場合に支給されるものや、職場環境の整備、教育訓練の実施などに対して支給されるものが含まれます。
たとえば、特定求職者雇用開発助成金では、重度障がい者等を雇用した場合、中小企業では最大240万円もの助成を受けることができますが、この制度の条件を満たしていない企業はこうした恩恵を受けられません。
このように、障がい者雇用に取り組まないことは、企業にとって経済的な機会損失となる可能性があります。
3. 法令違反リスクと企業イメージの低下
実雇用率の低い企業には、雇用率達成に向けた指導が行われることもあります。ハローワークからの雇入れ計画作成命令や、勧告・指導が行われ、それでもなお改善が見られない場合には、最終的に企業名が公表されるリスクも存在します。
企業名の公表は、法令を遵守していない企業というネガティブなイメージが広がり、社会的な信用を大きく損なうものです。これは、顧客や取引先との関係悪化、ブランドイメージの低下、さらには従業員の士気低下など、事業活動全体に多大な悪影響を及ぼしかねません。
法令遵守は企業活動の基本であり、障がい者雇用においてもその例外ではないことを認識しておく必要があるでしょう。
4. 多様性を欠いた組織の硬直化
障がい者を含む多様な人材がいない組織は、視点や発想が限定され、変化への対応力が低下するリスクがあります。
多様性のない組織では、同質的な考え方や価値観が強化される「グループシンク」と呼ばれる現象が起きやすくなります。これにより、新しいアイデアの創出や問題解決の幅が狭まり、イノベーションが生まれにくくなる可能性があるでしょう。
また、多様な背景を持つ人材がいないことで、顧客や市場の多様なニーズを理解し対応することが難しくなります。たとえば、障がいのある人の視点がなければ、製品やサービスの使いにくさに気づかず、潜在的な市場機会を逃してしまうかもしれません。
さらに、組織の硬直化は環境変化への適応力の低下につながります。多様な視点や考え方がない組織は、変化に対して柔軟に対応することが難しく、競争力の低下を招く恐れもあるでしょう。
このように、障がい者雇用に取り組まないことは、組織の創造性や適応力の観点からもデメリットとなり得るのです。
5. 採用競争力への悪影響
企業の社会的責任(CSR)に対する関心が高まる現代において、求職者は企業の理念や社会貢献活動にも注目しています。障がい者雇用に消極的な企業や、法定雇用率を大幅に下回っている企業は、社会的責任を果たしていないと見なされ、求職者にとって魅力的ではないと見なされる可能性があります。
特に、若い世代を中心に、企業のダイバーシティ&インクルージョンへの取り組みを重視する傾向が強まっています。多様な人材が活躍できる環境を提供していない企業は、優秀な人材の獲得競争において不利になるばかりか、既存の従業員のエンゲージメント低下にもつながりかねません。また、投資家も企業のESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを評価するようになっており、障がい者雇用への姿勢が投資判断に影響を与えるケースも考えられるでしょう。
障がい者雇用で活用できる相談窓口

企業が障がい者雇用を進めるにあたって、さまざまな疑問や課題に直面することがあります。そのような場合に、専門的な知識や情報を提供し、具体的なアドバイスを行ってくれる相談窓口を活用することが非常に有効です。
主な相談窓口としては、以下の公的機関が挙げられます。
- ハローワーク(公共職業安定所):全国に設置されており、障がい者専門の窓口では、求人の申込みや職業紹介だけでなく、障がい者雇用に関する全般的な相談に応じています。助成金制度の案内や申請受付も行っています。
- 地域障害者職業センター:各都道府県に設置されており、障がい者雇用に関する専門的な相談・援助サービスを提供。事業主に対して、障がいのある人の雇い入れ計画の作成支援、職場内での合理的配慮に関する助言など、きめ細やかなサポートを行っています。
- 障害者就業・生活支援センター:障がいのある人の就業面と生活面の一体的な支援を行う機関です。企業に対しては、雇用に関する相談に応じたり、雇用した障がいのある人の職場定着支援を行ったりしています。
これらの機関は、それぞれ特色があり、提供するサービスも多岐にわたります。自社の状況や課題に合わせて、これらの相談窓口を積極的に利用し、専門家からのアドバイスや支援を受けながら、障がい者雇用の取り組みを進めていくことが成功への近道となるでしょう。
障がい者雇用にProShare(プロシェア)を活用するという選択肢

本記事では、障がい者雇用の基礎知識、法律、メリット・デメリット、具体的な手順、さらに活用可能な助成金制度に至るまで、事業責任者の皆様が押さえておくべき情報を網羅的に解説しました。
障がい者雇用は、法的義務の履行に留まらず、企業価値の向上、組織の活性化、そして人手不足の解消にもつながる重要な経営戦略の一つです。しかし、その推進には専門的な知識やノウハウが不可欠であり、採用のミスマッチや定着率の課題、受け入れ体制の構築など、多くの企業が直面する課題も少なくありません。
こうした課題を乗り越え、障がい者雇用を成功に導くための一つの有効な手段が、ProShare(プロシェア)の活用です。経験豊富なプロ人材が、各企業の状況に応じた最適な雇用計画の策定から、採用・定着支援、社内理解の促進、助成金申請のサポートまで、実践的かつ包括的な支援を提供します。
第三者の視点と専門的なノウハウを取り入れることで、企業は障がい者雇用の課題を効率的に解決し、多様な人材が活躍できる職場環境の実現を目指すことができます。
\ 障がい者雇用の課題、ご相談ください /
課題の本質を見極め、プロの知見を活用した
最適な解決方法をご提案いたします。