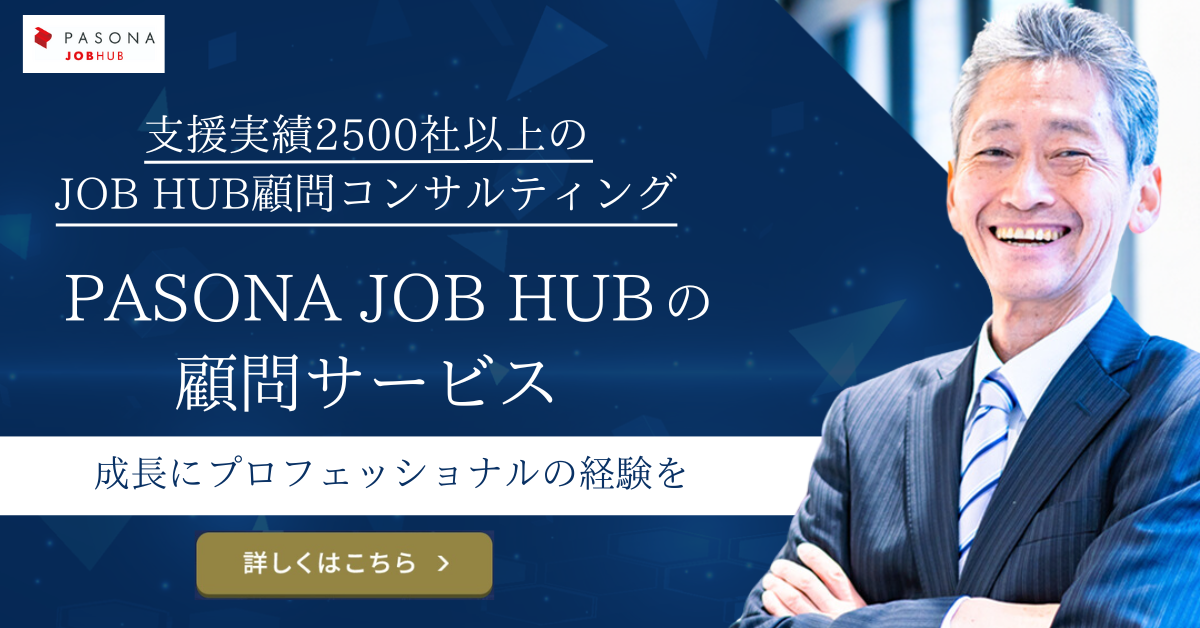近年、企業のデジタル化が加速する中で、IT戦略の重要性はますます高まっています。しかし、多くの企業では社内のIT人材不足や、専門知識の不足により、効果的なIT活用に苦戦している状況です。経済産業省の調査によれば、デジタル化を事業方針の優先事項と考える企業の割合は、2019年の40.3%から2021年には62.5%まで増加しました(※参考①)。
このような背景から、ITに関する豊富な経験と知識を持つ「IT顧問」の需要が高まっています。IT顧問は、企業のIT戦略立案から導入、運用までを包括的にサポートする専門家です。本記事では、IT顧問の役割や活用事例、料金相場、選び方のポイントなどを詳しく解説します。
目次
IT顧問とは?
IT顧問とは、ITに関する豊富な知見とノウハウを活かし、企業のIT戦略やシステム化を支援する専門家です。単なる技術的なアドバイザーにとどまらず、経営的な視点からIT活用の方向性を示し、企業の競争力向上に貢献する役割を担います。IT顧問の主な役割は、以下の3つに分類されます。
- IT戦略の立案と実行支援
- 企業の経営目標に沿った最適なIT投資計画の策定
- 中長期的な視点でのIT戦略立案
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
- システムの導入と最適化
- 新規システムの選定・導入支援
- 既存システムの改善提案
- クラウドサービスの活用推進
- ベンダーコントロール
- IT組織の強化
- ITリテラシー向上のための従業員教育
- セキュリティ対策の強化
- システム運用体制の整備
- エンジニア採用支援
特に近年では、コロナ禍を契機としたリモートワークの普及や、顧客ニーズの変化により、企業のIT活用の重要性は急速に高まっています。しかし、多くの企業ではIT人材の不足や専門知識の欠如により、効果的なデジタル化の推進に苦戦している状況です。そのため、外部の専門家であるIT顧問の需要が増加しているのです。
IT顧問とITコンサルの違い
IT顧問とITコンサルタントは、一見似たような役割に見えますが、支援の特徴や関わり方に違いがあります。以下の表で主な違いを比較してみましょう。
| IT顧問 | ITコンサルタント | |
|---|---|---|
| 支援範囲 | 柔軟に対応(戦略立案から実務まで) | 明確に定義された範囲内 |
| 課題発見 | 経営層との対話を通じて課題を発掘 | 与えられた課題に対してソリューションを提供 |
| 契約形態 | 月額での顧問契約が主流 | プロジェクトベースの契約 |
| 費用感 | 月額10~50万円程度 | プロジェクト総額で数百万円~ |
| コミュニケーション | 随時相談可能 | 定例会議やマイルストーン報告が中心 |
このように、IT顧問は企業により深く寄り添い、包括的な支援を提供する「伴走者」としての役割を果たします。一方、ITコンサルタントは特定のプロジェクトや課題に対して、専門的な知見を活かした解決策を提供することに特化しています。企業の状況や課題に応じて、以下のような使い分けが効果的です。
【IT顧問の活用が適しているケース】
- 中長期的なIT戦略の立案と実行が必要
- 継続的な相談相手が欲しい
- 経営視点からのアドバイスが必要
- 柔軟な支援範囲の調整が必要
【ITコンサルタントの活用が適しているケース】
- 特定のプロジェクトを短期間で完遂したい
- 明確な課題に対する専門的な解決策が必要
- 大規模なシステム刷新を計画している
- プロジェクト単位での成果物が必要
より詳しい情報については、IT・DX推進支援に関する資料をご覧ください。
IT顧問の料金相場と費用対効果
IT顧問の導入を検討する際、料金相場を理解することは重要な判断材料となります。IT顧問の契約形態は、主に「固定契約(月額制)」と「時間契約(スポット契約)」の2種類があり、企業の課題や予算に応じて選択できます。
以降では、契約形態別に料金相場と主な支援内容について解説します。
固定契約の料金相場
固定契約(月額制)は、毎月一定の顧問料を支払い、継続的なサポートを受ける契約形態です。以下に、企業規模別の一般的な料金相場をまとめました。
| 企業規模 | 料金目安 | 主なサービス内容 | 想定される支援頻度 |
|---|---|---|---|
| 中小企業向け | 10~40万円 | ・IT戦略助言 ・システム導入相談 ・セキュリティ対策支援 ・IT戦略立案支援 ・プロジェクト管理 ・ベンダー選定 ・交渉支援 ・デジタル化推進支援 | ・月1〜2回の定例会議 ・メール/電話での随時相談 ・週1回の定例会議 ・必要に応じた訪問支援 |
| 大企業向け | 50~100万円 | ・全社IT戦略の策定 ・大規模システム導入支援 ・DX推進支援 ・IT人材育成支援 | ・週2〜3回の定例会議 ・常駐型での支援も可能 |
料金は顧問の経験や専門性によって変動します。例えば、大手企業でのCIO経験者や、特定業界での豊富な実績を持つ顧問の場合、上記の料金帯よりも高額になることがあるでしょう。支援内容は、基本的な相談対応から実務的な支援まで、契約内容に応じて柔軟に設定できます。多くの企業では、まず小規模な契約からスタートし、効果を確認しながら支援範囲を広げていくアプローチを取ってる傾向です。
スポット契約(プロジェクト単位)の料金相場
時間契約(スポット契約)は、特定の課題や短期的なプロジェクトに対して、必要な時だけIT顧問の支援を受ける契約形態です。システム導入の検討段階や、重要な意思決定の場面で活用されることが多くあります。
| 契約単位 | 料金目安 | 主な活用シーン | サービス内容例 |
|---|---|---|---|
| プロジェクト単位 | 10万円~1,000万円 | ・緊急の技術相談 ・システムトラブル対応 ・システム導入検討 ・ベンダー選定会議 ・重要な意思決定支援 ・プロジェクト立ち上げ | ・技術的アドバイス ・問題解決支援 ・要件定義支援 ・提案書の評価 ・戦略策定支援 ・キックオフ会議への参加 |
料金は、顧問や業務内容によって変動します。短期間のスポット契約の場合、固定契約(月額制)よりも割高になるケースも多くあります。しかし、初めてIT顧問を活用する企業の場合、まずはスポット契約で支援の質を確認し、その後固定契約(月額制)に移行するというステップを踏むことが一般的です。
IT顧問の活用事例
IT顧問の活用は、業界や企業規模を問わず、さまざまな場面で効果を発揮しています。ここでは、実際の導入事例を通じて、IT顧問がどのように企業の課題解決に貢献したのかを見ていきましょう。
1. IT・金融業:デジタルバンキングの進化に伴うITシステム運用の高度化
セブン銀行は、コンビニATMの運営で知られる革新的な金融機関として、2001年の新規参入以来、国内で初めてスマートフォンによるATM入出金サービスを提供するなど、先進的な取り組みを積極的に行ってきました。しかし、技術革新が加速する中、高度なスキルを持つエンジニアの採用において課題を抱えていました。多くの企業がエンジニア採用に注力する中、応募者が思うように集まらず、また応募があっても最終的に他社を選択されるケースが続いていました。
この状況を打開するため、IT顧問の支援を受け、新しいアプローチ手法を取り入れました。
1つ目は、採用職種名の改善です。実際に欲しい人材が企画系にも関わらず、採用職種名に「社内SE」と表記しているなど、求めている職種が、エンジニア側にうまく伝わっていないケースがありました。そこでIT顧問から、エンジニアに刺さりやすい募集文言についてのアドバイスをもらいました。
2つ目は、転職エージェントとの関係構築です。エージェント向けの会社説明会を開催するなど、改めてエージェントとの関係を強化しました。
その結果、エージェントからの紹介案件の質が向上し、採用数の増加だけでなく、より高いスキルを持つエンジニアの採用にも成功。わずか3ヶ月という短期間で、採用活動の改善サイクルを確立することができました。
2. 製造業:基幹システムの刷新に伴うプロジェクトマネジメント不足
富士通ゼネラルでは、従来から部門ごとに異なるシステムが存在し、部門間の連携が取りづらい状況が続いていました。事業・経営上の意思決定の遅れを解消するため、SAPを全社的に導入することを決定しましたが、大規模プロジェクトのマネジメント経験を持つメンバーが少なく、またSAPに関する知見も不足している状況でした。コンサルティング会社や外部の開発会社に依頼はしていたものの、受発注という関係性の中で距離感が払拭できないまま進んでいました。
このような状況下で、IT顧問を導入したことで、プロジェクトの状況は大きく改善。顧問は単なるプロジェクトの牽引役としてだけでなく、上層部の意向と現場の最適な接続点を見出し、橋渡しする役割も担いました。特に、上層部の意向と現場での実装における落としどころを見出す能力は、現場経験が豊富な顧問ならではの強みとなりました。また、ITベンダーとのコミュニケーションが円滑になったことで開発スピードが大幅に向上し、プロジェクトメンバーの育成にもつながっています。
3. 金属加工業:DX推進における社内の意識改革と教育不足
バルブの製造・販売で70年以上の歴史を持つ株式会社キッツは、企業の持続的成長に向けて全社的なDX推進を決定しました。しかし、社内でDXに関する情報発信を行っても、興味を持つ社員が3分の1程度に留まるという課題に直面。企業変革に対する経験が不足している上、全社員を巻き込むような啓蒙活動や教育に関する知識・経験も不足している状況でした。そこで、変革経験豊富なIT顧問を導入し、組織全体の意識改革に取り組むことを決定しました。
IT顧問は、「誰を対象に、どうなってほしいか」というペルソナ設計から着手。社員の関心度合いによって必要な施策を変える、段階的なロードマップを作成しました。他社での実績に基づく豊富な情報量と、何度も議論を重ねることで、チーム全体が自信を持って施策を決定できるようになりました。特筆すべきは、顧問のアグレッシブな仕事への姿勢が、社員に良い刺激を与えた点です。男性が多い職場において、女性社員が遠慮しがちな風潮があった中、女性顧問のパワフルな仕事ぶりは、特に女性社員に大きなインパクトを与え、休憩時間にはキャリア相談に応じるなど、想定以上の波及効果をもたらしました。
IT顧問の選び方|企業に最適な専門家を見つける方法とは?
企業がIT顧問を選定する際には、単なる技術力だけでなく、自社の課題解決に最適な人材であるかを多角的に評価することが重要です。以下では、IT顧問選びの重要なポイントと、具体的な選定プロセスについて解説していきます。成功するIT顧問は、以下の5つのステップで選定していきましょう。
- 自社の目的と課題の明確化
- 必要なスキルと経験の定義
- 実績と評判の確認
- 契約形態と報酬の検討
- 面談による相性確認
各ステップについて、詳しく解説します。
1. 目的を明確にする
IT顧問を選ぶ際、まず重要なのは自社が抱える課題とその解決に向けた目的を明確にすることです。経済産業省の調査によれば、企業のデジタル化への取り組みは年々増加しており、2021年には62.5%の企業が事業方針の優先事項としています。しかし、多くの企業では具体的な推進方法や、どのような専門家に相談すべきかの判断に迷っているのが現状です。一般的に、企業がIT顧問に求める主な目的は以下の4つに分類されます。
- DX推進の加速(業務プロセスのデジタル化、データ活用基盤の構築)
- IT戦略の立案・実行(IT投資計画の策定、システム導入・刷新)
- 情報セキュリティの強化(セキュリティポリシーの策定、対応体制の構築)
- IT人材の育成・採用支援(採用戦略立案、技術者育成プログラムの策定)
また、実際の企業現場では「システム担当者の退職リスク」「社内エンジニアの人件費負担」「IT投資の費用対効果の不明確さ」といった具体的な課題認識からIT顧問の採用を検討するケースが多く見られます。これらの目的や課題を具体的に整理することで、必要とされる顧問のスキルや経験が明確になり、適切な人材選びにつながります。
2. 必要なスキルと経験を定義する
IT顧問に求められるスキルと経験は、企業の課題によって異なります。しかし、単なる技術力だけでなく、企業の状況を理解し、適切なソリューションを提案できる総合的な能力が重要です。成功事例を多く持つIT顧問に共通する必要なスキルは、以下の3つの領域に分類されます。
- 技術的スキル:クラウドインフラの設計・構築経験、アプリケーション開発の知見、セキュリティ対策の実務経験が基本となります。また、AI・IoTなどの新技術への理解も重要です。
- マネジメントスキル:プロジェクト管理やベンダーマネジメントの実績、チームビルディングの手法、予算管理の知見が求められます。セブン銀行の事例でも、エージェントとの関係構築や採用プロセスの改善など、マネジメントスキルが成功の鍵となりました。
- ビジネススキル:業界知識・動向の理解、経営戦略との整合性を図る能力、そして経営層や現場とのコミュニケーション能力が不可欠です。特に、技術的な内容を非技術者にもわかりやすく説明できる力は、重要な要素となります。
このように、技術・マネジメント・ビジネスの3つの領域でバランスの取れたスキルを持つIT顧問を選ぶことで、より効果的な支援を受けることができるでしょう。
3. 実績と評判をチェックする
IT顧問の実績と評判は、その人材の信頼性を判断する重要な指標となります。特に、過去の支援実績や課題解決の具体的なアプローチ方法を確認することが、選定の成功につながります。富士通ゼネラルの事例では、IT顧問の豊富な現場経験が、上層部と現場の効果的な橋渡しを実現し、プロジェクトの成功に大きく貢献しました。
実績と評判を確認する際の主なポイントは以下の3つです。
- 業界・規模の適合性:自社と同じような業界や規模の企業での支援実績があるかどうか。特に、類似した課題に対する具体的な解決事例の有無は重要な判断材料となります。
- プロジェクトの成果:過去のプロジェクトでどのような具体的成果を上げたのか。例えば、コスト削減額、プロジェクト期間の短縮度合い、システム導入後の運用状況などの定量的な実績を確認します。
- クライアントからの評価:継続率やリピート率、具体的な評価コメントなど。特に、長期的な支援実績がある場合は、持続的な価値提供が可能な人材であると判断できます。
これらの情報は、顧問紹介サービスや、直接の紹介元から詳細を確認することが望ましいでしょう。
4. 契約形態と報酬を比較する
IT顧問との契約形態の選択は、支援内容と自社のニーズに応じて慎重に検討する必要があります。契約形態によって得られるメリットや費用対効果が異なるため、自社の状況に最適な形態を選ぶことが重要です。一般的なIT顧問の契約形態は、以下の2つに分類されます。
- 月額固定契約:継続的な支援を受ける形態で、月額10~50万円程度が一般的です。IT戦略の立案から実行まで、包括的なサポートが必要な場合に適しています。キッツの事例でも、このタイプの契約により、全社的なDX推進を効果的に進めることができました。
- スポット契約(時間単位):必要な時だけ支援を受ける形態で、1時間あたり1~3万円が相場です。システム選定の相談や、技術的な質問など、明確な課題に対する解決策を得たい場合に適しています。初めてIT顧問を活用する企業や、特定のプロジェクトでの助言が必要な場合におすすめです。
契約期間は通常1年間で、その後は自動更新されるケースが多いですが、最初は3ヶ月程度の試用期間を設けることで、支援内容の質を確認することも可能です。
5. 実際に面談を実施する
IT顧問選定の最終段階として、実際の面談を通じて相性や具体的な支援内容を確認することが重要です。セブン銀行の事例では、最初の面談で「この人だ」と確信が持てたことが、その後の成功につながりました。面談では、技術力だけでなく、以下の3つの観点から総合的な評価を行うことが大切です。
- コミュニケーション能力:IT顧問の説明の分かりやすさ、質問への対応力、提案の具体性を確認します。技術的な内容を非技術者にも理解できるように説明できるか、また、自社の課題を的確に理解し、実現可能な解決策を提示できるかがポイントとなります。
- 問題解決アプローチ:自社の課題に対する分析の的確さ、解決策の現実性、実施手順の明確さを評価します。特に、「すぐにできること」と「時間をかけて取り組むべきこと」を区別し、優先順位をつけた提案ができるかどうかに注目します。
- 価値観の共有:企業文化との親和性、仕事への姿勢、チームワークの重視度合いなど、長期的な関係構築が可能かどうかを判断します。
面談時は、可能であれば複数の関係者で評価を行い、多角的な視点から判断することをおすすめします。また、具体的な支援計画や期待される成果について、明確な合意を得ることも重要です。
IT顧問なら顧問コンサルティングサービスへ
企業のIT戦略を成功に導くには、適切なIT顧問の選定が不可欠です。これまで見てきた通り、IT顧問は単なる技術アドバイザーではなく、企業の成長を支援する重要なパートナーとしての役割を果たします。
IT顧問の選定で特に重要なのが、企業の課題に対して適切な経験とスキルを持つ人材とのマッチングです。パソナJOB HUBの顧問コンサルティングサービスは、10,000名以上のプロフェッショナル人材の中から、企業の具体的な課題に最適な人材を紹介しています。例えば、DX推進、IT戦略立案、セキュリティ対策、システム選定など、幅広い領域で実績のある顧問を擁しており、2,500社以上の導入実績があります。
特に以下のような企業には、顧問コンサルティングサービスの活用がおすすめです。
- IT戦略の立案・実行に課題を感じている
- DX推進を加速させたい
- システム導入・刷新を検討している
- IT人材の採用・育成に悩んでいる
まずは貴社の課題やニーズについて、専門のコンサルタントが丁寧にヒアリングさせていただきます。課題解決に最適な人材を、最短1週間でご紹介することが可能です。
より詳しい情報や具体的なご相談は、以下のリンクからお問い合わせください。
\ ITの課題、ご相談ください /
課題の本質を見極め、プロの知見を活用した
最適な解決方法をご提案いたします。
※参考①:経済産業省:2022年版 中小企業白書 ・小規模企業白書概要