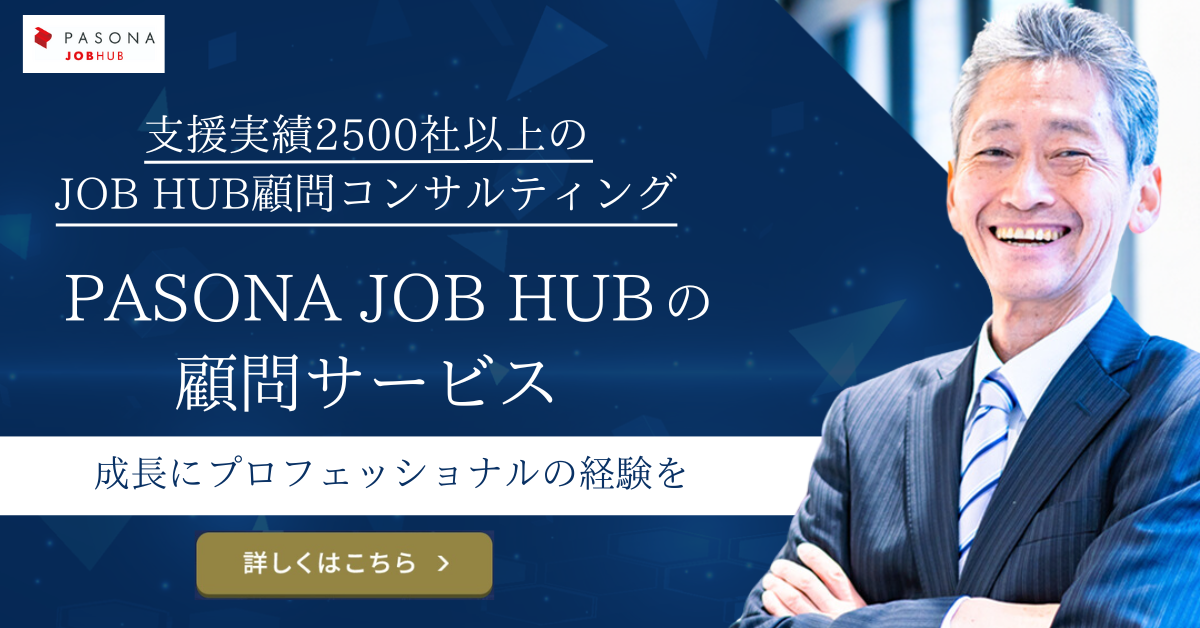近年、女性の社会進出が進む一方で、育児と仕事の両立に悩む社員が増えています。
特に、出産や育児を機に、本人の意思とは関係なくキャリアの選択肢が狭まってしまう「マミートラック」という現象が問題視されています。
企業の人事担当者や経営層にとって、この課題への対応は避けては通れない課題です。
本記事では、マミートラックの意味やなぜ起こるのかについて紹介。
さらに企業や社員(子を持つ親)にとってのメリット・デメリットや企業が取るべき対策について、具体的な事例を交えながら解説します。
育児支援制度導入のポイントもご紹介しますので、人材活用や職場環境の改善にお役立てください。
目次
マミートラックとは
「マミートラック」という言葉をご存知でしょうか。この用語は、1988年にアメリカで生まれたもので、特定の制度の名前ではなく、状況や問題を指す言葉として使われていました。
当初は「育児をしながら働く女性が選べるキャリアの選択肢」というポジティブな言葉として使われましたが、次第に「出世コースから外されるキャリアパス」という否定的なニュアンスが加わるようになりました。
日本では後者の意味で使われることが多く、「育児をしている女性が、本人の意思に反して出世コースから外れる状態」を指す言葉として認識されています。
特に問題視されているのは、育休復帰後に補助的な業務への配置転換や、重要なプロジェクトから外されるなど、キャリアの選択肢が狭められる状況です。これは企業の人材活用の面から見ても、大きな損失となっています。
マミートラックの意味は?
マミートラックは、英語の「Mommy(母親)」と「Track(軌道、進路)」を組み合わせた言葉です。出産・育児を機に、女性社員が従来のキャリアコースから外れ、昇進・昇格の機会が制限される状態を指します。具体的には、以下のような状況を示します。
- 育休復帰後に、補助的な業務への配置転換
- 重要なプロジェクトからの除外
- 時短勤務や柔軟な勤務形態の選択肢が限られる
- キャリアアップの機会が減少
このような状況は、本人の意思や能力とは関係なく発生することが多く、女性の活躍推進を妨げる要因となっています。
マミートラックはわがまま?
マミートラックは、育児をしながら働く女性の「わがまま」ではなく、むしろ深刻な社会的・構造的な問題を表す言葉です。令和5年に公表された厚生労働省の調査によると、第一子出産後も働き続ける女性は年々増えているものの約5割に留まっており、その背景にはさまざまな社会的障壁が存在します。(※参考①)
企業の中には「育児中の女性への配慮」という名目で、本人の意向を確認せずに補助的な業務への異動や、責任の軽い仕事への配置転換を行うケースがあります。しかし、これは真の意味での「配慮」とはいえません。
これらの課題を解決するには、育児と仕事の両立を支援する制度の整備と、固定的な性別役割分担意識の見直しが必要です。
なぜマミートラックは起こるのか?
では、マミートラックはなぜ起こるのでしょうか。
マミートラックが発生する主な要因として、次の5つが挙げられます。
- 社会的役割の期待
- 職場環境の不十分な支援
- キャリアパスの不均衡
- 育児と仕事の両立の難しさ
- 男女の不平等な家庭責任の分担
これらの要因は相互に関連しており、企業の制度や文化の改革なくしては解決が困難です。
それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
社会的役割の期待
日本社会には、依然として「育児は女性が担うべき」という固定観念が根強く残っています。総務省の調査(2021年)によれば6歳未満の子どもを持つ夫婦の家事及び育児時間は、女性が1日7時間28分に対し、男性はわずか1時間54分に留まっています。(※参考②)
このような社会通念は職場にも影響を及ぼし、「育児中の女性社員には責任ある仕事を任せられない」という偏見を生み出しています。結果として、本人の意思や能力に関係なく、補助的な業務に回されるケースが少なくありません。
企業にとって重要なのは、このような固定観念から脱却し、個々の社員の意欲と能力に応じた適切な業務配分を行うことです。社会的役割への期待と実際の能力は別物であることを、組織全体で認識する必要があります。
職場環境の不十分な支援
多くの企業では、育児と仕事の両立を支援する制度が十分に整備されていない、もしくは制度はあっても実際の利用が難しい状況が続いています。厚生労働省の調査によると、令和3年度における育児休業制度の規定がある事業所は、事業所規模30人以上で95.0%、5人以上で79.6%と高い水準です。(※参考③)しかし、令和5年度の女性の育休取得率は84.1%、男性は30.1%と大きな開きがあります。(※参考④)
特に問題なのは、フレックスタイムや時短勤務、在宅勤務といった柔軟な働き方の選択肢が限られていることです。制度があったとしても「利用することで周囲に負担がかかる」「評価に影響するのではないか」という懸念から、利用を躊躇する社員も少なくありません。結果として、育児中の女性社員は従来の働き方を維持することが困難となり、キャリアの選択肢が狭まってしまうのです。
キャリアパスの不均衡
育児期間中の女性社員のキャリア形成には大きな課題があります。厚生労働省の調査によると、令和5年度における管理職(課長相当以上)に占める女性の割合は12.7%に留まっており、特に育児期間中の女性はキャリア継続に課題を抱えやすく、昇進が難しいケースもあるといわれています。(※参考④)
この背景には、出産や育児による一時的な業務の中断や、時短勤務への移行が、その後のキャリアに大きく影響を与えている実態があります。多くの企業では、育児中の社員を重要なプロジェクトから外したり、責任の軽い業務に配置転換したりする傾向があります。また、残業や突発的な業務対応が難しいことを理由に、昇進や重要な役職への登用機会が制限されることも珍しくありません。
このような状況は、本人の能力や意欲とは無関係に、育児期間中の働き方の制約がそのままキャリアの制約となってしまう「マミートラック」の典型的な例といえます。
育児と仕事の両立の難しさ
育児をしながらフルタイムで働く社員は、日々さまざまな課題に直面しています。特に子どもが小さい時期は、保育園の送迎や急な発熱への対応、定期的な健診や予防接種など、想定外の事態が頻繁に発生します。
さらに、子どもの成長に伴い、保育園や学校の行事参加、PTA活動など、平日の日中に時間を確保する必要のある用事も増えていきます。
このような状況下で定時の勤務を続けることは、物理的にも精神的にも大きな負担となります。結果として、キャリアを継続するか、育児に重点を置くかの選択を迫られるケースも少なくありません。
男女の不平等な家庭責任の分担
先述の通り、総務省の調査では、6歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児時間は、妻が1日7時間28分に対し、夫はわずか1時間54分となっています。この数字は、欧米諸国と比較しても著しく格差が大きく、日本における家庭責任の偏りを如実に示しています。(※参考②)
このような不平等な負担により、女性社員は仕事に充てられる時間やエネルギーが制限され、キャリア形成に支障をきたすことになります。
また、急な残業や休日出勤への対応が難しいことから、重要なプロジェクトから外されるなど、結果的にマミートラックに陥るケースも多く見られます。この状況を改善するためには、家庭内での公平な役割分担と、それを可能にする企業の理解や支援が不可欠です。
マミートラックのメリットとは?
マミートラックには、一般的にネガティブなイメージが強いものの、企業と社員の双方にとって一定のメリットが存在します。ただし、これらのメリットは一時的なものであり、長期的な視点では組織の成長や人材活用の観点から再考が必要な部分も多くあります。
以下では、企業側と社員側それぞれの立場から、マミートラックがもたらすメリットについて詳しく見ていきましょう。これらの理解は、より効果的な両立支援制度を構築する上で重要な示唆を与えてくれます。
マミートラックによる企業へのメリット
企業にとってマミートラックには、人員配置や業務管理の面で以下のようなメリットがあります。
まず、育児中の社員を定型的な業務に配置することで、急な休暇や早退があっても業務の引き継ぎや代替が比較的容易になります。
また、責任の重い職務から外すことで、突発的な対応や長時間労働が必要な場面での人員不足のリスクを軽減できます。
さらに、時短勤務などの制度利用により人件費の抑制にもつながり、短期的には経営効率の面でプラスになる可能性があります。ただし、これらは一時的なメリットであり、長期的には優秀な人材の成長機会を失うことにもなりかねないため、要注意です。
マミートラックによる社員(子供を持つ親)へのメリット
育児中の社員にとって、マミートラックには以下のような実質的なメリットがあります。
まず、時間的な融通が利きやすくなります。定型的な業務が中心となることで、急な早退や休暇の取得がしやすくなり、子どもの急な発熱や学校行事への参加にも対応しやすくなります。
また、業務負荷の調整が可能になります。責任の重い仕事や長時間労働を避けられることで、育児に必要な時間とエネルギーを確保できます。実際、育児中の女性社員の中には、一時的にでもこのような働き方を望む声もあります。
さらに、同じように育児をしている社員が多い職場環境では、互いの状況を理解し合える同僚との関係も築きやすく、精神的な負担の軽減にもつながります。ただし、これらのメリットは、あくまでも本人の意思による選択である場合に限られることを覚えておきましょう。
マミートラックのデメリットとは?
マミートラックは、企業と社員の双方に深刻な影響を及ぼします。特に長期的な視点で見ると、組織の成長力低下や人材流出、キャリア形成の停滞など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
これらのデメリットは、企業の持続的な発展や、働く人々のワークライフバランスに大きく関わる問題です。以下では、企業側と社員側それぞれの立場から、マミートラックがもたらす具体的なデメリットと、その解決に向けた取り組みについて詳しく見ていきましょう。
マミートラックによる企業へのデメリット
マミートラックは企業に対して、人材活用と企業価値の両面で大きな損失をもたらす可能性があります。特に重要なのは、優秀な人材の能力が十分に活かされないことによる組織全体の生産性低下です。
また、女性の活躍に消極的という評価は、企業イメージの低下や人材採用への悪影響にもつながります。
この課題に対し、先進企業では具体的な対策を講じています。
例えば資生堂では、出産後に復職する社員を対象とした「ウェルカムバックセミナー」を実施し、仕事と育児の両立に対する不安の軽減に努めているほか、リモートワークとオフィスワークを組み合わせた柔軟な働き方を導入。(※参考⑤)(※参考⑥)
メルカリでは、子どもの看護休暇を最大10日間まで取得可能とし、ベビーシッター費用の補助も行っています。(※参考⑦)
また、りそなホールディングスでは、子どもが小学校6年生まで利用できる「職種間転換制度」を設け、育児中の社員のキャリア継続を支援しています。(※参考⑧)
マミートラックによる社員(子供を持つ親)へのデメリット
育児中の社員個人にとって、マミートラックによる最大のデメリットは、キャリア形成の機会が制限されることです。単純作業や補助的な業務が中心となることで、スキルアップの機会が減少し、昇進・昇格の可能性も低くなります。
また、給与面でも、時短勤務による収入減少に加え、評価が低くなりがちな傾向があります。これらの問題に対する具体的な対処法としては、以下の取り組みが効果的です。
- 上司との定期的なコミュニケーション
- 今後のキャリアプランについての相談
- 業務内容の見直しの要望
- 評価基準の確認
- 両立支援制度の活用
- フレックスタイム制度の利用
- 在宅勤務の活用
- 保育サービスの利用
- 自己啓発の継続
- オンライン学習の活用
- 業界動向のキャッチアップ
- 社内外のネットワーク構築
これらの取り組みを通じて、育児期間中もキャリアを維持・発展させることが可能になるでしょう。
育児支援制度導入のポイント
前述のマミートラックのデメリットや問題を解消し、育児と仕事の両立を実現するには、企業による効果的な支援制度の整備が不可欠です。
多くの企業では、以下の4つの要素を中心に、自社の状況に合わせた支援制度を構築しています。
- 柔軟な働き方の提供
- フレックスタイム制度
- 在宅勤務制度
- 時短勤務制度
- 時差出勤制度
- 育児休業後の復職支援
- 育休中のスキルアップ研修
- 定期的な情報共有機会の設定
- 段階的な職場復帰プログラム
- キャリア相談窓口の設置
- 周囲の理解促進
- 管理職向け研修の実施
- 育児経験者との対話機会の創出
- 両立支援制度の社内周知
- ダイバーシティ推進研修
- サポート環境の整備
- 事業所内保育施設の設置
- ベビーシッター費用の補助
- 育児中の社員同士のネットワーク構築
- 育児経験者によるメンター制度
先に紹介した資生堂やメルカリなどの先進企業の事例を見ると、これらの施策は企業規模や業界を問わず導入可能です。
ただし、これらの制度を導入する際は、自社の状況や課題に合わせてカスタマイズすることが重要です。
また、制度の利用状況や社員の声を継続的に収集し、効果検証と改善を重ねることで、より実効性の高い支援体制を築くことができるでしょう。
マミートラックの解決に向けてプロ人材の利用がおすすめ
労働人口減少や多様性の確保などの観点から、今後ますます、企業の成長には女性の活躍が欠かせなくなっていきます。
今回ご紹介したマミートラックなど、女性のキャリア形成に負の影響を与える問題には、早急に対応する必要があります。
女性活躍には、組織風土の改革から制度設計まで、包括的なアプローチが必要です。
中でも「社内にロールモデルとなる女性管理職がおらず、女性社員がキャリア形成のイメージを持てない」という問題に、多くの企業が頭を悩ませています。
このような課題に対してパソナJOB HUBが提供しているのが、社外メンターサービス。
次世代経営者・事業責任者に、弊社のプロ人材が外部メンターとして育成支援を行います。
短期的な研修ではなく長期的な伴走支援のため、一過性ではない継続的な成長を促進できます。
女性活躍に向け一歩踏み出したい方、まずはお気軽にご相談ください。
\ 女性活躍の課題、ご相談ください /
JOB HUB顧問コンサルティングの
次世代経営者・事業責任者向けメンターサービスでは
女性活躍・ダイバーシティ推進の支援も行っています。
※参考①:厚生労働省|第一子出産前後の妻の継続就業率・育児休業利用状況(令和5年5月30日)
※参考②:総務省統計局|我が国における家事関連時間の男女の差~生活時間からみたジェンダーギャップ~
※参考③:厚生労働省|令和3年度雇用均等基本調査
※参考④:厚生労働省|令和5年度雇用均等基本調査
※参考⑤:株式会社資生堂|働きがいのある職場の実現