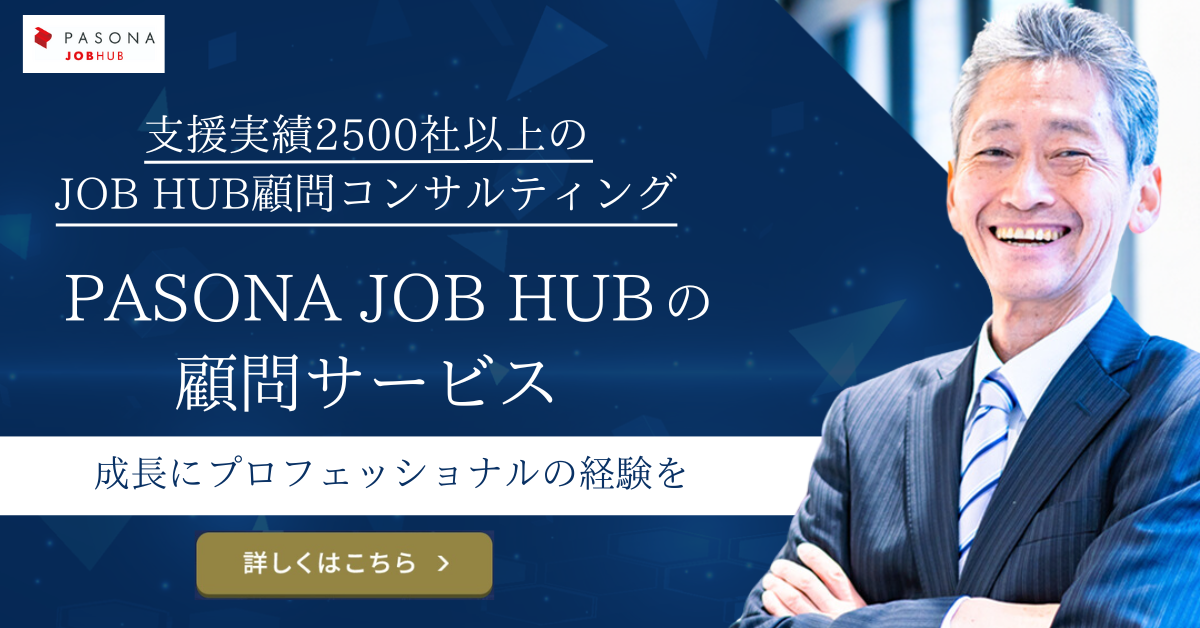事業責任者として、従業員の労働時間削減に取り組む中で、「時短ハラスメント(ジタハラ)」という新たな人事課題に直面していませんか。
「働き方改革」を推進する一方で、意図せず従業員を追い詰めてしまうケースは少なくありません。
この記事では、時短ハラスメントが具体的にどのような行為を指すのか、その定義から実例、企業が被る深刻なデメリットまでを掘り下げて解説します。さらに、発生の原因を紐解き、実効性のある対策、そして万が一問題が発生した際の適切な企業対応についてもご紹介します。
目次
時短ハラスメント(ジタハラ)とは

時短ハラスメント(ジタハラ)とは、労働時間や業務量を削減するための具体的な方策を示さずに、会社が労働者に対して残業を制限したり、定時退社を強要したりする行為を指します。「時間短縮ハラスメント」の略語で、2018年にはユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされ、社会的な認知度も高まっています。
働き方改革の本来の目的は、従業員の心身の健康を守りながら生産性を向上させることです。しかし、表面的な残業時間の削減にばかり注目し、実質的な業務改善を行わないことで、従業員は定時退社を強いられながらも、終わらない仕事を自宅に持ち帰ったり、タイムカードを押した後に隠れて仕事を続けたりせざるを得ない状況に追い込まれます。
時短ハラスメントの特徴として、管理職が部下の残業時間削減のプレッシャーを受け、部下の仕事を引き受けて長時間労働に陥るケースも多く見られます。このような状況は、組織全体の健全性を損ない、最悪の場合は過労死や精神疾患といった深刻な問題に発展する可能性があるのです。
▼ハラスメント対策・防止についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム┃ProShare(プロシェア)
時短ハラスメントの具体例

時短ハラスメントは、一見すると働き方改革を推進しているように見えながら、実際には従業員に過度な負担を強いる行為です。職場で起こりやすい時短ハラスメントの典型的なパターンを理解することで、自社の問題の早期発見・解決につながります。以下では、実際の職場で頻繁に発生する5つの具体例を詳しく見ていきましょう。
1. 定時退社を強要されるが、業務量はそのまま
「残業は禁止だから、定時までに終わらせて」という指示が出される一方で、実際の業務量は従来と変わらないケースが典型的な時短ハラスメントです。
たとえば、これまで月60時間の残業をして処理していた業務を、何の業務改善もなく「今月から残業ゼロで」と命じられる状況が該当します。
このような場合、従業員は物理的に不可能な要求に直面し、結果として品質を犠牲にして急いで仕事を終わらせるか、持ち帰り残業をせざるを得なくなります。管理職から「時間内に終わらないのは能力不足」と評価される恐れもあり、精神的なプレッシャーも相当なものになるでしょう。
2.無理な納期設定
短期間での納品を求められながら、作業時間は定時内に限定されるという矛盾した状況も時短ハラスメントの一例です。「明後日までに企画書を仕上げて」と指示されても、他の業務との兼ね合いや必要な調査・検討時間を考慮すると、明らかに時間が足りないスケジュール設定がされるケースがあります。
特に問題となるのは、納期設定の際に現場の意見が反映されず、上層部の都合だけで決められることです。「顧客との約束だから」「上司の指示だから」という理由で、現実的でない納期が押し付けられ、従業員は板挟みの状態に置かれてしまいます。
3.サービス残業・持ち帰り残業の強要
表向きは「ノー残業デー」や「定時退社推進」を掲げながら、実際には「家でやっておいて」「明日の朝一番に提出して」といった形で、事実上の時間外労働を指示するケースが存在します。残業申請を出そうとすると「評価に響く」「管理職としての能力が問われる」といった圧力がかかることもあるでしょう。
こうした状況下では、従業員は自己防衛のために残業を申告せず、サービス残業や持ち帰り残業を選択してしまいます。企業側は表面上の残業時間削減を達成できたように見えますが、実態は労働基準法違反の温床となっている可能性が高いのです。
4. 業務過多への訴えを無視
従業員が「業務量が多すぎて時間内に終わらない」と上司に相談しても、「それは工夫で何とかなるよ」「他の人はできているのに」といった返答で、具体的な解決策が提示されないケースがあります。業務量の調整や人員補填の要望を真剣に検討せず、個人の問題として片付けてしまう対応は典型的な時短ハラスメントといえるでしょう。
このような環境では、従業員は孤立感を深め、「自分の能力が低いのかもしれない」と自己否定に陥りやすくなります。実際には組織的な問題であるにもかかわらず、個人の責任に転嫁されることで、メンタルヘルスの悪化につながる危険性があるのです。
5. 生産性向上の名の下に非現実的なKPIを強制
「定時退社できていないのは君の生産性が低いから」という評価を下し、業務プロセスの改善や必要なツールの導入といった支援なしに、一方的に高い生産性目標を課すケースも問題です。たとえば、「作業時間を半分に短縮」「処理件数を2倍に」といった非現実的なKPIが設定され、達成できなければ個人の責任として処理されます。
真の生産性向上には、業務フローの見直し、ITツールの活用、スキルアップのための研修など、組織的な取り組みが不可欠です。しかし、こうした投資や改革を行わずに、単に数値目標だけを押し付けることは、従業員を追い詰めるだけの結果に終わってしまいます。
過去に時短ハラスメントが認められた判例
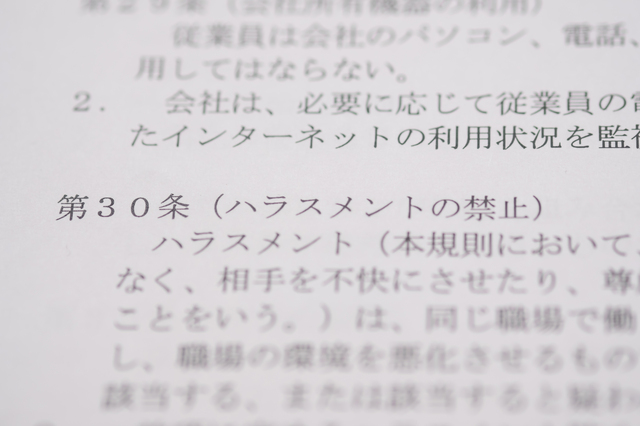
時短ハラスメントは単なる職場の問題にとどまらず、実際に裁判で企業の責任が問われ、労働災害として認定されたケースも存在します。以下では、時短ハラスメントが深刻な結果を招いた実例を通じて、企業が負うべき法的責任と、問題の重大性について理解を深めていきましょう。
これらの判例は、適切な労働時間管理と業務量調整の重要性を示す重要な教訓となっています。
1. 店長の過労自殺と企業の謝罪
2018年に和解という形で決着した、ある自動車販売店での悲劇的な事例があります。
新規オープンした店舗を任された店長は、開店準備で残業が続く中、会社からは部下の残業時間を減らすよう強く指示されていました。責任感の強い店長は、部下の残業を減らすために自ら仕事を引き受け、持ち帰り残業が常態化していきました。
結果として、店長はうつ病を発症し、不当にも解雇されてしまいます。さらに悲劇的なことに、解雇の無効を求める労働審判の最中に、店長は自ら命を絶ってしまいました。労働基準監督署はこの自殺の原因を過大な仕事量と認定し、労災として認定しています。
遺族が損害賠償を求めた裁判では、会社側は「ご本人、ご家族に深い悲しみと精神的苦痛を負わせてしまった」と謝罪し、企業としての責任を認めました。この事例は、時短ハラスメントが単なる労務管理の問題ではなく、従業員の生命に関わる重大な問題であることを示しています。
2. 持ち帰り残業による労災認定と残業代支払い命令
PCのシステム保全を担当するエンジニアのAさんは、業務量が多いにもかかわらず、上司から休日出勤や長時間の残業を禁止されていました。しかし、実際の業務は到底時間内に終わる量ではなく、Aさんは仕事を持ち帰らざるを得ない状況に追い込まれていきました。
継続的な持ち帰り残業により、Aさんは業務過多が原因で体調を崩してしまいます。最終的に、Aさんは会社に対して持ち帰り残業分の支払いなどを求めて裁判を起こしました。
裁判所は、持ち帰り残業の部分を含めると「時間外労働がおおむね80時間を超える範囲に達していた」と推認し、会社に対して労災の認定と残業代の支払いを命じました。この判例で重要なのは、一般的に自主的な持ち帰り残業は「残業」とみなされないものの、定時帰宅を強要するプレッシャーがある場合には「残業」として認定されるという点です。
3. 出退勤記録と異なる実労働が「労働時間」と認定
ある企業では、従業員が自己申告した終業時刻と、実際の業務実態が大きくかい離していることが問題となりました。裁判では、パソコンの使用ログ、メールの送信記録、社用車の運転記録など、さまざまな客観的証拠を基に実際の労働時間が認定されました。
特に注目すべきは、従業員が月30時間という残業時間の上限に合わせて申告していた実態が明らかになったことです。裁判所は、会社側が月30時間以内に残業時間を抑えるよう指導していたことを認定し、従業員が実際の労働時間を過少申告せざるを得ない環境にあったと判断しました。
この判例は、形式的な労働時間管理では不十分であり、実態に即した適正な把握が必要であることを示しています。企業は、従業員が正直に労働時間を申告できる環境を整備する責任があるのです。
4. 「創意くふう提案」やQC活動が業務と認定
製造業の現場でよく行われる「創意くふう提案」やQCサークル活動について、これらが労働時間に該当するかが争われた事例があります。企業側は「自主的な活動」と主張しましたが、裁判所は異なる判断を下しました。
裁判所は、これらの活動が人事考課の対象となっていること、全員参加が求められていること、賞金が交付されること、さらに企業の生産活動に直接貢献していることなどを総合的に判断し、「業務」として認定。つまり、所定労働時間外に行われるこれらの活動も、労働時間として扱われるべきだという判断です。
この判例は、企業が「自主的」と位置づける活動であっても、実質的に強制力が働いている場合は労働時間として認定される可能性があることを示しています。働き方改革を進める際は、こうした周辺的な業務についても適切に管理する必要があるでしょう。
時短ハラスメントが発生する原因とは
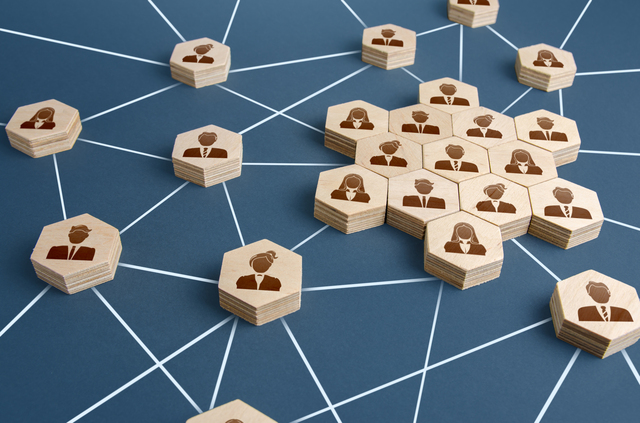
時短ハラスメントは、単に個人の管理能力の問題ではなく、組織全体の構造的な課題から生じることが多いのが実情です。働き方改革という大きな目標と、日々の業務遂行という現実の間でギャップが生じ、そのしわ寄せが現場の従業員や中間管理職に集中してしまうのです。
最も大きな原因は、経営層と現場の認識のずれにあります。経営層は「残業時間を削減すれば生産性が向上する」という理想論を掲げますが、実際の業務量や必要な作業時間を正確に把握していないケースが多く見られます。各部署が抱える業務の複雑さや、顧客対応の実態、繁忙期と閑散期の差など、現場の実情を理解せずに一律の時短目標を設定することで、実現不可能な要求となってしまうのです。
また、業務プロセスの見直しや効率化への投資が不十分であることも大きな要因となっています。ITツールの導入、業務の自動化、不要な会議の削減など、本来であれば時短と同時に進めるべき施策が後回しにされ、「とにかく早く帰れ」という指示だけが先行してしまいます。
人材不足も深刻な問題です。適正な人員配置がなされていない状況で時短を進めれば、必然的に一人当たりの業務負荷は増大します。特に日本企業では「頑張ればなんとかなる」という精神論に頼りがちですが、構造的な人手不足を個人の努力で補うことには限界があります。
さらに、管理職の評価制度も時短ハラスメントを助長する要因となっています。部下の残業時間削減が管理職の重要な評価指標となっている一方で、業務成果や品質維持も同時に求められるという矛盾した状況が、管理職を板挟みの状態に追い込んでいるのです。
時短ハラスメントが企業に与えるデメリット
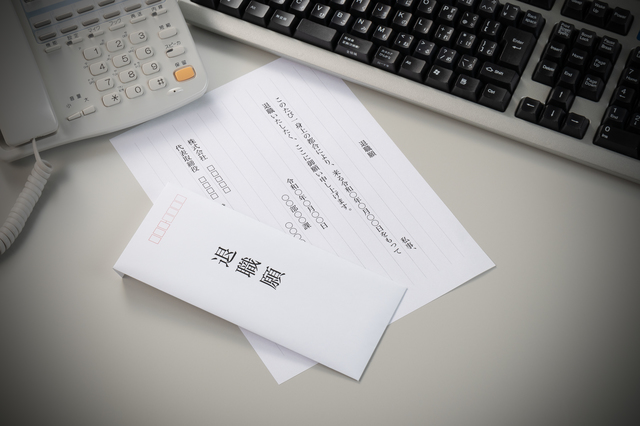
時短ハラスメントは、表面的には労働時間の削減という成果を生み出しているように見えますが、実際には企業に深刻なダメージを与える可能性があります。短期的な数値改善にとらわれ、従業員の健康や組織の持続可能性を軽視した結果、取り返しのつかない損失を被ることになりかねません。以下では、時短ハラスメントが企業経営に及ぼす具体的な悪影響について、詳しく解説していきます。
生産性低下
時短ハラスメントによる最も直接的な影響は、組織全体の生産性低下です。
従業員が時間内に仕事を終わらせることだけに注力し、品質や創造性が犠牲になってしまうケースが頻発します。たとえば、十分な検討時間が取れないまま企画書を作成したり、確認作業を省略して納品したりすることで、手戻りやクレームが増加する結果となります。
モチベーションの低下も深刻な問題です。正当な評価を受けられず、サービス残業を強いられる環境では、従業員の仕事に対する情熱は失われていきます。「どうせ頑張っても評価されない」という諦めの気持ちが広がれば、イノベーションや改善提案も生まれにくくなり、組織の競争力は確実に低下していくでしょう。
休職・離職の増加
時短ハラスメントによる過度なストレスは、従業員の心身の健康を蝕みます。実際に、持ち帰り残業や精神的プレッシャーが原因でうつ病を発症し、休職に追い込まれるケースは少なくありません。メンタルヘルスの問題は本人だけでなく、周囲の同僚にも影響を与え、職場全体の雰囲気を悪化させる要因となります。
優秀な人材の離職も避けられません。特に若手社員は、不合理な労働環境に見切りをつけ、より良い条件の企業へ転職していく傾向があります。採用コストは一人当たり数百万円に上ることも珍しくなく、さらに育成にかけた時間と費用を考えれば、企業にとっての損失は計り知れません。残された社員への負担も増大し、離職の連鎖を招くリスクもあります。
イメージ低下
現代はSNSの時代であり、企業の内部事情は瞬く間に外部に伝わります。時短ハラスメントの実態が、退職者の口コミサイトやTwitterなどで拡散されれば、企業のブランドイメージは大きく損なわれることになるでしょう。「ブラック企業」というレッテルを貼られてしまえば、優秀な人材の採用は困難になり、取引先からの信頼も失いかねません。
特に若い世代は、企業の労働環境に関する情報に敏感です。就職活動の際には必ず企業の評判をインターネットで調べる時代において、時短ハラスメントの噂は致命的なダメージとなります。一度失った信頼を回復するには、相当な時間と努力が必要となることを認識しておく必要があります。
時短ハラスメントの対策方法とは

時短ハラスメントを防ぎ、真の働き方改革を実現するためには、表面的な残業時間削減ではなく、組織全体の仕組みを根本から見直す必要があります。従業員の健康と企業の生産性を両立させるには、経営層から現場まで一体となった取り組みが不可欠です。
以下では、時短ハラスメントを防ぐための具体的な対策について、実践的な観点から解説していきます。
業務量を減らす
根本的な解決策として最も重要なのは、業務量そのものを適正化することです。まず現状の業務を棚卸しし、本当に必要な業務とそうでないものを明確に区別する必要があります。長年の慣習で続けている定例会議や報告書作成など、実際には価値を生んでいない業務は思い切って廃止することも検討すべきでしょう。
業務の優先順位を明確にすることも大切です。すべての業務を100%の品質で行うのではなく、重要度に応じてメリハリをつけることで、限られた時間を有効活用できます。たとえば、社内向けの資料は簡素化し、顧客向けの提案書に注力するといった判断が必要になってきます。
人材不足を補う
慢性的な人手不足は時短ハラスメントの温床となります。適正な人員配置を行うためには、各部署の業務量と必要工数を正確に把握し、データに基づいた人員計画を立てることが重要です。単に頭数を増やすだけでなく、スキルや経験を考慮した適材適所の配置により、組織全体の効率を高めることができます。
業務の属人化を解消することも急務です。特定の従業員しかできない業務があると、その人に負担が集中し、休暇も取りづらくなります。マニュアルの整備や複数担当制の導入により、業務を標準化・共有化することで、柔軟な人員配置が可能となります。また、繁忙期には派遣社員やアウトソーシングの活用も検討すべきでしょう。
生産性を高める
DXの推進は生産性向上の鍵となります。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の自動化、クラウドツールを活用した情報共有の効率化、AIを使った業務支援など、テクノロジーの力を最大限に活用することで、人間にしかできない付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることができます。
働き方そのものの見直しも必要です。フレックスタイム制やテレワークの導入により、従業員が最も生産性の高い時間帯や場所で働けるようにすることで、限られた時間でより多くの成果を生み出すことが可能になります。また、会議の効率化(アジェンダの事前共有、時間厳守、オンライン活用など)も、すぐに実践できる改善策といえるでしょう。
ハラスメント防止の仕組みづくり
組織として時短ハラスメントを防ぐためには、明確なルールと仕組みの構築が必要です。厚生労働省が示すパワーハラスメント防止指針(参考①②)を参考に、時短ハラスメントも含めた包括的なハラスメント防止規程を整備することが第一歩となります。規程には、具体的な禁止行為、相談窓口、調査手順、処分基準などを明記し、全従業員に周知徹底することが重要です。
管理職教育も欠かせません。部下の労働時間管理だけでなく、業務配分の適正化、メンタルヘルスケア、コミュニケーションスキルなど、総合的なマネジメント能力を向上させる研修を定期的に実施する必要があります。また、相談窓口を設置し、従業員が安心して問題を報告できる環境を整えることで、問題の早期発見・解決につながるでしょう。
従業員が時短ハラスメントを訴えた場合の企業体制

従業員から時短ハラスメントの訴えがあった場合、企業は迅速かつ適切に対応する必要があります。初動対応を誤ると、問題が深刻化し、訴訟リスクや企業イメージの毀損につながる可能性があるからです。ここでは、訴えを受けてから再発防止までの一連の対応フローについて、具体的に解説していきます。
事実関係の調査
時短ハラスメントの訴えを受けたら、まず冷静に事実関係を調査することから始めます。被害を訴えた従業員からは、いつ、どこで、誰から、どのような行為を受けたのか、具体的な状況を詳細に聞き取ります。感情的にならず、中立的な立場で傾聴することが大切です。同時に、メールやチャット、勤怠記録などの客観的な証拠も収集します。
加害者とされる人物や周囲の関係者からも事情を聴取する必要があります。ただし、この段階では予断を持たず、あくまでも事実確認に徹することが重要です。調査の過程で新たな事実が判明することもあるため、柔軟に対応できる体制を整えておく必要があります。また、調査中は関係者のプライバシーに配慮し、情報管理を徹底することも忘れてはいけません。
委員会の設置
重大な事案や組織的な問題が疑われる場合は、調査委員会を設置することが望ましいでしょう。
委員会のメンバーには、人事部門だけでなく、法務部門、労働組合の代表、さらには弁護士や社会保険労務士などの外部専門家を含めることで、客観性と専門性を確保できます。
委員会では、収集した証拠を基に事実認定を行い、時短ハラスメントに該当するかどうかを判断します。判断に当たっては、労働基準法や判例、厚生労働省のガイドラインなどを参考にしながら、慎重に検討しましょう。また、調査結果と今後の対応策について報告書をまとめ、経営層に提出することで、組織としての意思決定を明確にすることができます。
再発防止
調査の結果、時短ハラスメントの事実が認定された場合は、速やかに是正措置を講じるとともに、再発防止策を実施します。加害者に対しては、行為の重大性に応じて指導、配置転換、懲戒処分などの措置を検討します。被害者に対しては、心理的ケアや業務環境の改善など、必要な支援を行うことが重要です。
組織全体の再発防止策としては、まず今回の事案から得られた教訓を全社で共有することから始めます。管理職研修を強化し、適切な労務管理の方法を再教育します。また、業務プロセスの見直しや人員配置の適正化など、構造的な問題の解決にも取り組む必要があるでしょう。定期的なアンケート調査やヒアリングを実施し、新たな問題の芽を早期に発見できる仕組みを構築することも効果的です。
時短ハラスメント対応の見直しなら

時短ハラスメントは、働き方改革の本来の目的を見失った結果生じる深刻な問題です。
従業員の健康と企業の生産性を両立させるためには、表面的な残業時間削減ではなく、業務プロセスの抜本的な見直しと、組織文化の変革が必要となります。
自社の対応体制を見直す際は、まず現状を正確に把握することから始めましょう。従業員の声に耳を傾け、実際の労働実態を客観的に分析することで、問題の本質が見えてきます。そして、経営層から現場まで一体となって、持続可能な働き方改革を推進していくことが重要です。
しかし、組織内部だけでこうした改革を進めることは容易ではありません。客観的な視点と専門的な知識を持つ外部専門家の支援を受けることで、より効果的な対策を講じることができます。労務管理の専門家は、法的リスクの回避はもちろん、組織の実情に合わせた実践的なアドバイスを提供してくれるでしょう。
パソナJOB HUBのProShare(プロシェア)には、ハラスメント対応のプロ人材が多数登録しています。経験豊富なコンサルタントが貴社の状況に合わせ、最適なプロ人材とソリューションをご提案します。健全な組織づくりと持続的な成長のために、ぜひ一度ご相談ください。
\ ハラスメントの課題、ご相談ください /
課題の本質を見極め、プロの知見を活用した
最適な解決方法をご提案いたします。
参考②:厚生労働省|職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)