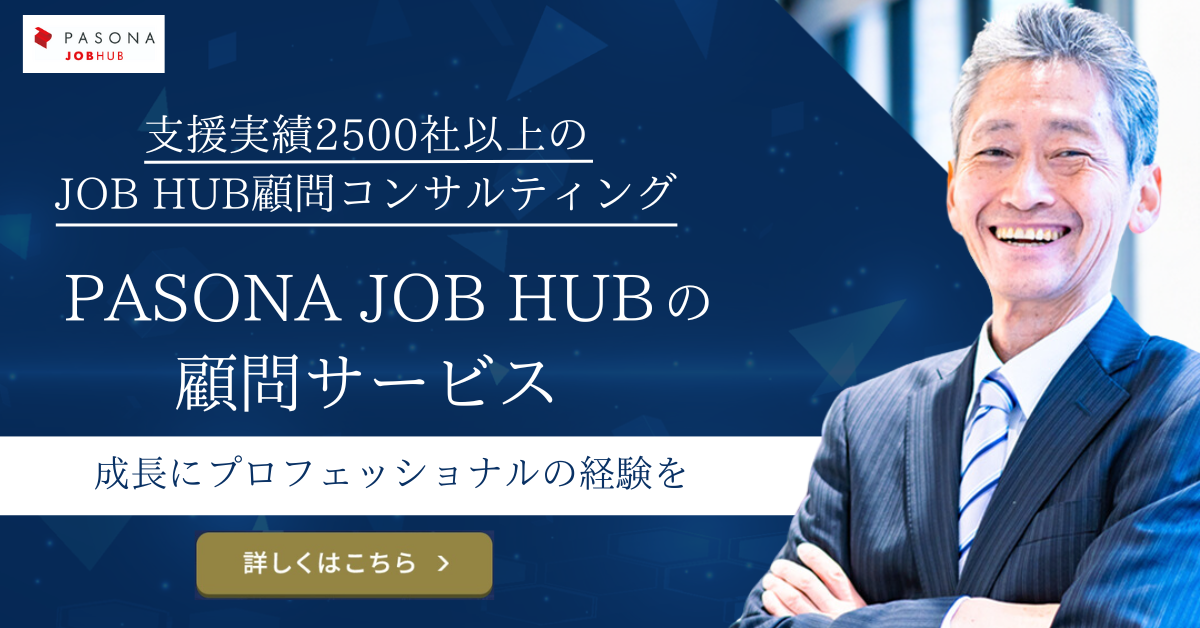近年、多くの企業が人材不足に直面しており、シニア人材の活用が注目を集めています。しかし、「シニア人材をどのように活用すれば良いのか分からない」「若手社員とのコミュニケーションに不安がある」といった声も多く聞かれます。
本記事では、シニア人材の活用を考慮している経営層・企業担当者の向け、人材活用のメリットやデメリット、具体的な成功事例について解説します。
目次
シニア人材活用とは?
シニア人材活用とは、60歳以上の人材が持つ豊富な経験や専門知識を企業の成長に活かす取り組みです。
総務省の統計によると、日本の生産年齢人口は2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると予測されており、多くの企業が人材確保に課題を抱えています(※参考①)。
そのため、2021年には高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用確保が企業の義務となり、70歳までの就業機会確保も努力義務として定められました(※参考②)。このような法整備も、シニア人材活用を後押ししています。
実際に、シニア人材の活用は人材不足の解消にとどまらず、その豊富な経験や専門知識が企業の競争力強化にも大きく貢献しています。また、内閣府の調査によると、60歳以上の就業者の約9割が「70歳以降も働きたい」と回答しており、シニア層の就労意欲の高さも活用を促進する要因となっています(※参考③)。
シニア人材活用のメリット
長年の実務経験を持つシニア人材の活用には、企業にとって多くのメリットがあります。主なメリットは以下のとおりです。
- 豊富な経験と即戦力
- 労働力の確保
- 職場の多様性向上
以下、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
豊富な経験と即戦力
シニア人材の最大の強みは、長年培ってきた実務経験です。特に専門職や技術職では、若手では代替が難しい高度なスキルや知識を持っています。
例えば、製造業における熟練工の技術や、営業職における顧客との信頼関係など、長年の経験でしか得られない価値を企業にもたらします。また、業界特有の商習慣や暗黙知を理解しているため、新規プロジェクトの立ち上げや、重要な交渉事にも即座に対応できるでしょう。
さらに、過去の成功体験や失敗経験を基に、的確な判断や提案ができることも大きな強みです。このような経験に基づく知見は、若手社員の育成や技術伝承にも活かすことができます。
労働力の確保
深刻化する人材不足において、シニア人材の活用は解決策の一つです。総務省の労働力調査によると、65歳以上の就業者数は年々増加傾向にあり、2023年には過去最多の914万となっています(※参考④)。
特に、建設業や製造業など、若手の採用が困難な業界では、シニア人材の豊富な経験と技術が重宝されています。また、シニア人材は仕事に対する責任感が強く、勤務態度も安定していることから、職場の基盤となる人材として期待できます。
さらに、シニア人材の多くは、短時間勤務やフレックスタイムなど、柔軟な働き方を希望する傾向です。これにより、企業側も必要な時期や時間帯に適切な人員を配置することが可能となります。
職場の多様性向上
シニア人材の活用は、職場における世代間の多様性を高める効果があります。異なる年代の従業員が協働することで、多様な視点や考え方が生まれ、組織全体の創造性が向上します。
具体的には、シニア人材の経験に基づく慎重なアプローチと、若手社員の新しい発想や技術を組み合わせることで、より質の高い問題解決が可能になります。また、シニア人材が若手社員のメンターとして活躍することで、技術やノウハウの伝承がスムーズに進むという利点もあるでしょう。
さらに、多様な年齢層が存在する職場では、お互いの強みを活かし合える環境が自然と形成され、組織の対応力や柔軟性が高まることも期待できます。
シニア人材活用の課題
シニア人材の活用には、多くのメリットがある一方で、いくつかの課題もあります。主な課題は、以下のとおりです。
- 健康問題
- 給与水準とコスト
- 適材適所の配置
以下、主要な課題について詳しく見ていきましょう。
健康問題
シニア人材の活用において、最も配慮が必要なのが健康面です。年齢を重ねることで、体力や視力、聴力などの身体機能が徐々に低下することは避けられません。
厚生労働省の調査によると、60歳以上の労働者の労働災害発生率は、30代と比較して男性で約2倍、女性で約4倍に上ります(※参考⑤)。このため、定期的な健康診断の実施や、作業環境の改善、適切な休憩時間の確保など、きめ細かな健康管理が必要です。
また、フレックスタイムや短時間勤務など、柔軟な勤務形態を導入することで、シニア人材の体力的な負担を軽減することも重要です。このような配慮により、シニア人材が長期的に活躍できる環境を整えることができます。
給与水準とコスト
シニア人材の処遇、特に給与水準の設定は慎重な検討が必要です。長年の経験を持つシニア人材は、これまでの給与水準が比較的高い場合が多く、そのまま継続雇用すると企業の人件費負担が大きくなる可能性があります。
一方で、過度な給与削減はモチベーションの低下を招く恐れがあります。定年後再雇用時の給与は、定年前の20~40%程度減で設定されているケースが一般的です。このため、職務内容や勤務時間に応じた適切な給与水準を設定し、シニア人材と企業の双方が納得できる制度設計が求められます。
また、年金受給との兼ね合いや、高年齢雇用継続給付金などの助成金制度も考慮に入れながら、総合的な処遇を検討することが重要です。
適材適所の配置
シニア人材の効果的な活用には、個々の能力や経験を適切に評価し、最適な職務に配置することが重要です。しかし、これまでの経験や役職にとらわれすぎると、組織の新陳代謝が滞る可能性があります。
特に注意が必要なのは、若手社員の成長機会を阻害しないよう配慮することです。シニア人材に重要なポストを任せすぎると、若手社員のキャリア形成に支障をきたす可能性があります。シニア人材の経験を活かしつつ、若手の育成も両立させるバランスの取れた人材配置が求められます。
このような課題に対しては、メンター制度の導入や、技術伝承の役割を担う専門職ポストの新設など、シニア人材の強みを活かせる新たな職務設計も効果的です。
シニア人材活用の成功事例
シニア人材の活用において、実際に成果を上げている企業の取り組みを見ていきましょう。
株式会社ノジマでは、定年後の再雇用契約を上限80歳までとする制度を導入し、シニア人材の活躍を推進しています。さらに、シニア社員の給与体系は正社員と同一としながらも、勤務日数・時間を柔軟に調整できる仕組みを構築。これにより、シニア人材が無理なく長期的に活躍できる環境を実現しています(※参考⑥)。
また、三井情報株式会社では、シニア人材の活用に向けて、人事顧問を導入しています。シニア向け人事制度や評価者研修の設計において、経験豊富な顧問人材からアドバイスを得ることで、より実効性の高い制度構築を実現。Well-being経営に関する相談にも、専門家の知見を活かしながら方向性を定めています。
これらの成功事例に共通するのは、シニア人材の経験や知識を最大限に活かせる役割を明確に設定し、柔軟な働き方を可能にする制度を整備している点です。また、若手社員との協働を促進する仕組みづくりにも注力しており、世代を超えた知識やスキルの共有が実現されています。
特に三井情報の事例では、パソナJOB HUB顧問コンサルティングを活用し、人事部向けの勉強会を開催するなど、シニア人材の活用に向けた人事制度の構築にも取り組んでいます。外部の専門家の知見を借りながら、自社に適したシニア人材活用の形を模索している好例といえるでしょう。
シニア人材活用の課題と注意点
シニア人材を効果的に活用するためには、いくつかの課題に取り組む必要があります。具体的には、以下の3点です。
- 社内制度と人事制度の整備
- 柔軟な働き方の導入
- スキルの適切な活用と育成
これらの課題に適切に対応することで、シニア人材の能力を最大限に引き出すことができるでしょう。以下で詳しく解説します。
社内制度と人事制度の整備
シニア人材が活躍できる環境づくりの基盤となるのが、適切な社内制度の整備です。
まず重要なのは、公平で透明性の高い評価制度の確立です。シニア人材の経験や貢献を適切に評価し、それを処遇に反映させる仕組みが必要です。また、定年後の再雇用や継続雇用に関する制度も、労使双方が納得できる内容にする必要があります。
シニア人材の評価制度を整備している企業では、従業員の満足度が高く、生産性も向上する傾向が見られます。具体的には、役割や責任に応じた等級制度の導入や、成果に基づく報酬体系の整備などが効果的です。また、65歳超雇用推進助成金などの支援制度を活用することで、制度整備にかかるコストを軽減することも可能です。
柔軟な働き方の導入
シニア人材の活躍を支えるためには、個々の状況に応じた柔軟な働き方を可能にする制度が不可欠です。
例えば、短時間勤務やフレックスタイム制の導入、在宅勤務の活用など、多様な勤務形態を用意することで、体力面での不安や介護などの家庭事情にも対応できます。また、業務の一部を切り出して分担するジョブシェアリングの導入も、シニア人材の負担軽減に効果的です。
さらに、勤務日数や時間を調整できる選択制の導入により、シニア人材が自身の体力や生活スタイルに合わせて働き方を選択できるようになります。このような柔軟な制度は、シニア人材のモチベーション維持にも寄与するでしょう。
スキルの適切な活用と育成
シニア人材の持つスキルを最大限に活かすためには、適切な配置と継続的な育成が重要です。
まず必要なのは、個々のシニア人材が持つスキルや経験の正確な把握です。長年の実務経験で培った専門知識や技術、人脈などを詳細に把握し、それらを活かせる業務への配置を検討します。例えば、若手社員の指導役や技術伝承の担当、重要顧客との関係維持など、経験が強みとなる役割への配置が効果的です。
また、新しい技術やビジネス環境の変化に対応するため、継続的な学習機会の提供も欠かせません。特にデジタル技術に関する研修やリカレント教育の実施は、シニア人材の活躍の幅を広げることにつながります。定期的な研修を実施している企業では、シニア人材の生産性が向上し、若手社員との協働もスムーズになる傾向が見られます。
シニア活用なら人事課題解決のプロ人材におまかせ
これまで見てきたように、シニア人材の活用にはさまざまな課題がありますが、適切な対策を講じることで、企業の大きな強みとなります。しかし、自社だけでこれらの課題に対応するのは容易ではありません。
パソナJOB HUB顧問コンサルティングでは、豊富な経験を持つ人事のプロフェッショナルが、シニア人材活用に関する課題解決をサポートしています。10,000名以上の登録コンサルタントの中から、企業の状況に最適な人材をご紹介し、制度設計から運用まで一貫してサポートいたします。
シニア人材の活用について、以下のような課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
- 高齢者雇用制度の整備や見直しをしたい
- シニア人材の評価・処遇制度を構築したい
- 世代間のコミュニケーションを改善したい
- 技術・ノウハウの継承を効果的に進めたい
貴社の課題に応じた最適なソリューションをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
\ 人事制度の課題、ご相談ください /
課題の本質を見極め、プロの知見を活用した
最適な解決方法をご提案いたします。
※参考①:総務省|令和4年版 生産年齢人口の減少
※参考③:内閣府|令和6年版高齢社会白書(全体版)
※参考④:総務省|統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-
※参考⑤:令和5年 高年齢労働者の労働災害発生状況|厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課
※参考⑥:シニア人材活用に向けて、知見を活かすため、人事顧問の導入を決定 「雇用上限80歳」で注目ノジマ 働くシニア社員はどう活躍? 78歳・石澤さん「週3日勤務、4日は自由に過ごせる」- イザ!