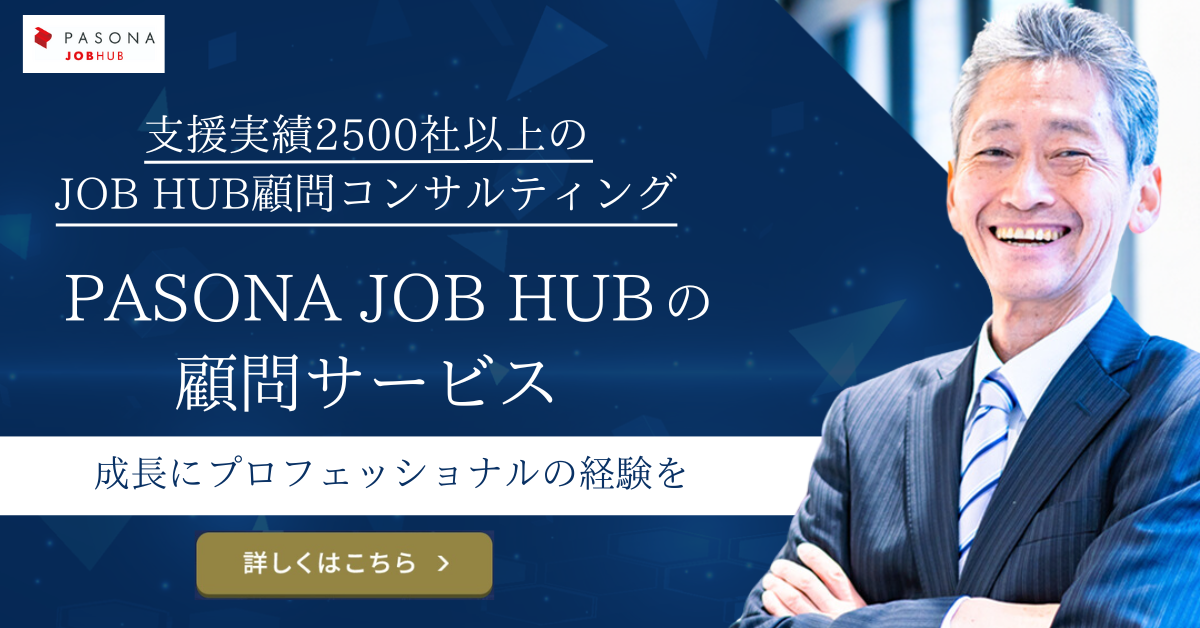燃え尽き症候群は、今までやる気に満ちていた人が急にやる気を失ったように見えてしまう状況です。社員の心身の健康を損なうだけでなく、職場全体の生産性低下や離職率の増加を引き起こすため、原因や前兆を踏まえた対策が欠かせません。
この記事では、燃え尽き症候群の定義やなりやすい人の特徴、燃え尽き症候群に至る前兆について紹介します。また、企業が燃え尽き症候群を未然に防ぎ、社員を守るために実践できる具体的な対策も併せて解説します。
目次
燃え尽き症候群とは?
燃え尽き症候群(バーンアウト症候群)とは、これまで高いモチベーションを持って取り組んでいた人が、突然やる気を失ってしまう状態のことです。医学的にはうつ病の一種とされており、長期間にわたる過剰なストレスやプレッシャーが原因で心身が疲弊した結果として起こります。
燃え尽き症候群は自覚しづらく、気づかないまま仕事や日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。燃え尽き症候群を引き起こす要因には、個人的なものと環境的なものがあるため、企業や個人が予防に努めることが重要です。
燃え尽き症候群になりやすい人とは?
燃え尽き症候群は誰にでも起こる可能性がありますが、なりやすい人には一定の特徴があります。ここでは、それぞれのタイプごとに、燃え尽き症候群になりやすい人の特徴や過程、職業や状況に伴う具体的なリスクについて解説します。
- 責任感が強い人
- 完璧主義者
- 断れない人
- 感情移入が強い人
- 休むことに罪悪感がある人
責任感が強い人
責任感が強い人は、他者からの信頼が厚くなる傾向があります。
しかし、周囲の期待に応えようと自分を犠牲にしたり、自分だけで問題を解決しようと抱え込んでいたりすれば大きなストレスになり得ます。
たとえば、プロジェクトリーダーが自分を犠牲にしてトラブル対応をすべて自分で行っていたり、休む間もなく業務に追われる状況が長期化したりすると、身も心も疲れ果ててしまいます。ストレスが高まっているなかで、ちょっとした休暇やミスなどで不意に気が緩むと、一気に燃え尽き症候群になることがあるのです。
完璧主義者
完璧主義者は、常に高い基準を目指して業務に取り組むため、時間やエネルギーを過剰に費やしてしまうことで燃え尽き症候群になりやすい傾向があります。
たとえば、提出した資料に細かいミスがあると、それを許せず何度も作り直してしまうケースが典型的です。すべてのデータの最新化を目指して必要以上に時間をかけてしまうこともあります。
また、他人からの評価に敏感な場合、周囲から正当に評価が受けられていないと感じてしまうことも少なくありません。完璧を追い求める姿勢が強いほど、自らの負担を軽減できず悪循環に陥ることがあるのです。
断れない人
断れない人は、他者からの依頼や期待に応えたいという気持ちが強すぎるために、自分の負担を増大させてしまいます。
業務量を調整できず長時間労働や過剰なタスクに追われていると、結果的に業務が積み重なりパンクしてしまうかもしれません。
たとえば、事務職の社員が同僚「この仕事をお願いできる?」と言われるままにすべて引き受けた結果、残業が常態化してしまうケースがあります。特に、チームプレイが重視される職場では、断りにくい環境が燃え尽き症候群に至るリスクを高めます。
感情移入が強い人
感情移入が強い人は、他者の悩みや感情に深く共感しすぎて精神的な負担になることがあります。また、共感力が高い場合、職場での人間関係やチームの問題にも敏感で、他者の感情を気にするあまり、自分の負荷を軽減できずに燃え尽き症候群になりやすい傾向があります。
たとえば、カスタマーサポート担当者が顧客の怒りや不満に対して共感しすぎて業務時間外でも顧客対応のことが頭から離れないケースや、介護士が利用者の問題に真剣に向き合いすぎて、自分のストレス発散や休息を後回しにしてしまうケースがあります。
休むことに罪悪感がある人
休むことに罪悪感がある人は、自分をいたわることが優先できず心身の疲労が蓄積する傾向があります。
他者への責任感や職場の期待を優先するあまりに、休息を取ることが悪いことだと考えて働き続けた結果、燃え尽き症候群になりやすいと言えます。
たとえば、育児や介護と両立して働いている社員が、体調不良でも休むことを躊躇し、無理を重ねて結果的に体調をさらに悪化させてしまうケースがあります。また、業務上強い負担を抱えている経営者や管理職にも同様の問題を抱えやすい傾向があります。
燃え尽き症候群になりやすい職業とは?
燃え尽き症候群は、特定の職業で特にリスクが高くなることがあります。その背景には、職業ごとの特性や責任感、感情的な負荷などが関わっています。ここでは、燃え尽き症候群になりやすい職業の特徴とそれぞれのリスク要因について解説します。
- 対人援助職(感情労働が多い職業)
- 高ストレス・高プレッシャーな職業
- クリエイティブ職・IT関連職
- シフト勤務や過労が多い職業
- 社会的期待が高い職業
1. 対人援助職(感情労働が多い職業)
医師、看護師、介護士、カウンセラー、教師、保育士などの対人援助職は、他者の感情やニーズに寄り添う業務が多く、自分の感情をコントロールして働く感情労働の負荷が非常に高い職業です。
対人援助職は、失敗が他者の生活や健康に直接影響するため、常に高い集中力と正確性が求められるためにストレスを感じやすく、燃え尽き症候群になりやすいです。
たとえば、医師や看護師、介護士は、夜勤や緊急対応による不規則な勤務時間が日常的で、睡眠不足や生活リズムの乱れが健康に影響を及ぼします。
教師や保育士は子どもたちや生徒の成長や安全に深く関わる責任を負いながら、保護者対応や事務作業など幅広い業務に追われることが少なくありません。
カウンセラーや介護士のように他者の感情に寄り添う職業では、相手に共感するあまり疲労が蓄積しやすく、心身のバランスを崩しやすい傾向があります。
2. 高ストレス・高プレッシャーな職業
営業職、経営者、弁護士、金融アナリストなどの職業は、成果を求められる環境や重い責任感が常に付きまとうため、高いストレスやプレッシャーにさらされることが特徴です。
これらの職業では、目標達成や意思決定が日常的に求められ、それが精神的な負荷を大きくする要因となり、燃え尽き症候群になりやすいです。
たとえば、営業職では、毎月の売上目標に対するプレッシャーや顧客対応のストレスが蓄積しやすく、成果が出ない場合は自己否定感につながることがあります。
経営者や弁護士は、組織やクライアントの重要な判断を担うため、一度のミスが大きな損失を生む可能性があり常に緊張を強いられます。
金融アナリストのように、市場変動に即座に対応する職業では、長時間の集中力と迅速な判断力が求められ、疲労が慢性化しやすい傾向があるのです。
3. クリエイティブ職・IT関連職
デザイナー、エンジニア、ライター、ゲーム開発者などのクリエイティブ職やIT関連職は、創造性や技術力が求められる一方で、締切や修正依頼に追われることも多いため、燃え尽き症候群になりやすい職業です。限られた時間のなかで独創的なアイデアを生み出すプレッシャーや、品質への細かなこだわりが、精神的な負担を増大させる要因となります。
たとえば、デザイナーはクライアントの要望に応じて細部を何度も修正することが多く、納期に追われる中で作業を完了させるプレッシャーが大きくのしかかります。
エンジニアはシステム開発やトラブル対応において、バグの修正や長時間にわたる集中作業が求められるため、疲労が蓄積しやすい環境です。特にIT関連職では、技術の進歩が速いため、スキルを磨き続けなければならないという心理的な負担も加わります。
ライターやゲーム開発者は、締切に間に合うようにクリエイティブな成果物を仕上げる必要があり、常に時間に追われるストレスを抱えています。
4. シフト勤務や過労が多い職業
警察官、消防士、飲食業、物流業(配送ドライバー)など、シフト勤務や過労が多い職業は、仕事が他者の安全やサービス品質に直結するため、責任感が重く、ストレスの逃げ場が見つけにくいことも特徴です。
肉体的な負担と精神的なストレスが複合的に重なることから、心身の疲労が蓄積しやすい傾向があり、燃え尽き症候群になりやすい職業です。
たとえば、警察官や消防士は、緊急対応が求められる場面が多く、夜間勤務や突発的な業務が生活リズムを崩す要因となります。
飲食業のスタッフは、慌ただしく長時間働き続けることが多く、顧客対応のストレスも加わるため、心身の負担が大きくなります。
物流業の配送ドライバーは、繁忙期には過密スケジュールでの運行が求められることが多く、疲労や睡眠不足が安全性や健康に悪影響を与える可能性があります。
5. 社会的期待が高い職業
アスリート、芸能人、政治家などの社会的期待が高い職業は、常に注目を浴びる環境で働くため、過度な期待やプレッシャーからのストレスが極めて大きい職業です。
常に成果や結果を求められるだけでなく、日常的に多くの人々の期待や批判にさらされることもあるため精神的な負担を感じやすく、燃え尽き症候群になりやすい職業です。
たとえば、アスリートは試合での結果がキャリアに直結するため、日々の厳しいトレーニングや試合でのプレッシャーを抱え続けます。失敗が大きく取り上げられることで、自己評価が低下し、心身のバランスを崩す要因になることも少なくありません。
芸能人は、メディアやSNSでの批評や中傷にさらされることが日常化しています。プライベートを守ることも難しく、常に気を張り詰めた状態が続くことがあります。
政治家は、重要な政策決定や発言が広範囲に影響を与えるため、失敗の許されない緊張感を抱えることが多く、長時間労働や批判のストレスが心身の負担となります。
燃え尽き症候群の前兆とは?
燃え尽き症候群の最も顕著な前兆の一つが、業務態度や生産性の変化です。
それぞれの前兆に応じた適切な対応策を取ることで、燃え尽き症候群を防ぎ、社員の健康と職場の生産性を保つことが可能です。
主な前兆は次のとおりです。
- 業務態度や生産性の変化
- コミュニケーションの変化
- 外見や生活態度の変化
- 会議やチーム活動での異変
- 過剰な労働や仕事の抱え込み
これらの前兆について、1つ1つ詳しく確認していきましょう。
業務態度や生産性の変化
業務態度や生産性の変化は、長時間労働や過度なストレスが原因で心身が限界を迎えているサインと言えます。
業務態度や生産性の変化による燃え尽き症候群の前兆は次のとおりです。
- これまで積極的に仕事に取り組んでいた社員の意欲が失われている
- 以前は目標達成を重視していた人の成果が低下する
- 周りから仕事の質が落ちている、最近たるんでいると言われる
- すぐに気が散ってしまい、簡単な作業でも業務に集中できなくなる
- 自分の仕事は誰でもできる価値のないものだと感じる
コミュニケーションの変化
燃え尽き症候群の前兆として自分をストレスから守るための反応として他人との関わりを避けたり、周囲に攻撃的になったりする場合があります。
コミュニケーションの変化による燃え尽き症候群の前兆は次のとおりです。
- 普段は明るく話し好きだった人が、会話を避けるようになり、無口になる
- チームの会話に加わらず、独りで作業を進める
- 感情的になりやすく、些細なことでイライラする
- 小さな意見の違いに過剰に反応するなど、よく怒るようになる
- 他人の話を遮る、意見を聞かなくなる
外見や生活態度の変化
身だしなみが変化したり、今までの生活態度が変化することも燃え尽き症候群の可能性があります。
外見や生活態度の変化による燃え尽き症候群の前兆は次のとおりです。
- これまで身だしなみに気を使っていた社員が、突然無頓着になり服装が乱れる
- 身体がだるく、モチベーションや集中力が低下する
- 頭痛や胃痛など、原因がはっきりしない身体的な不調が続く
- 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚めてしまう
- 体調を崩してからなかなか治らない
- 休んでも疲れが取れず朝に起きられない
- 会社に向かう足取りが重く、出勤しても早く帰りたいと思う
- 以前より飲むお酒の量が増える
会議やチーム活動での異変
これまで積極的に参加していた人が、チーム活動での情報共有や相談を避けるようになった場合、燃え尽き症候群が原因となっている可能性があります。
会議やチーム活動での異変による燃え尽き症候群の前兆は次のとおりです。
- 会議やチーム活動で意見を述べることが減り、消極的になる
- 会議中に発言しなくなり、質問にも簡単な答えしか返さない
- 会議中、他人の発言に興味を示さなくなる
- 以前は会議の進行役を務めていた社員が、役割を進んで引き受けなくなる
- 遅刻や欠席が増える
- 必要な資料や準備を忘れる
過剰な労働や仕事の抱え込み
責任感の強さや完璧主義などから、仕事に対して過度な責任感から過剰に抱え込むことがあります。
この場合、燃え尽き症候群につながるだけでなくパフォーマンスの低下や健康への悪影響を招く可能性があります。
過剰な労働や仕事の抱え込みによる燃え尽き症候群の前兆は次のとおりです。
- 残業が増えているのに成果が上がらない
- 他人に頼ることを嫌がり、すべてのタスクを抱え込む
- 同僚や上司への相談や協力を拒み、孤立する
- プライベートの生活を犠牲にしてでも仕事の完璧さを目指す
- 求められていないことも完璧にやろうとする
燃え尽き症候群への対策:企業が取るべきアクションとは
燃え尽き症候群を予防し、社員の心身の健康を守ることは、企業にとって重要な課題です。適切な対策を講じることで、生産性向上や離職率低下につながります。
以下では、企業が取るべき具体的なアクションを解説します。
- 社員の負担軽減
- コミュニケーションの促進
- メンタルヘルスの支援
- 休暇取得の推進
- 教育・トレーニングの提供
- 外部リソースの活用
1. 社員の負担軽減
社員本人が、「不調の原因が単なる疲労なのか」「心理的な要素が関わっているのか」を判断できない場合には、職場の上司や同僚など周囲の気づきと助言が重要です。
社員の負担軽減は、燃え尽き症候群を防ぐ最も基本的な対策です。
まず、業務量の適正化を図るため、各社員の業務内容や負担を定期的に確認しましょう。
もし負担が大きいと感じられる場合には、業務の再分担が必要かもしれません。場合によっては、休職などで仕事から一時的に距離を取ることも有効です。
また、業務範囲の明確化も重要です。役割や責任が不明確な状態はストレスを引き起こす原因となります。時間管理体制の見直しや公平な評価制度の導入など、従業員が意欲的に働ける環境づくりを意識することで、各自が負担を感じすぎずに仕事が進められます。
2. コミュニケーションの促進
コミュニケーションの促進は、燃え尽き症候群の要因となるストレスの早期発見や適切な対応に欠かせません。
管理職が定期的に1on1ミーティングを実施して、社員の業務に対するプライベートの悩みを聞きとることで、社員が抱える心理的負担を軽減できます。
ただし「みんな同じ条件で働いている」「またミスをされたら職場全体が困る」「がんばれば絶対にできる」のように、上辺だけの励ましや意見の押し付けにならないような配慮が重要です。相手に寄り添った対応を心がけましょう。
また、社員が自由に意見を言える環境を整えることで、チーム内での心理的安全性の確保やストレス軽減が図れます。チームワークや同僚の支え合いを奨励して社員の努力を適切に評価する体制をつくることで、協力的な職場環境の構築に役立ちます。
3. メンタルヘルスの支援
燃え尽き症候群を予防し、社員が健康的に働ける職場環境を整えるためには、社員一人ひとりのメンタルヘルスを支援する取り組みが欠かせません。
外部の心療内科やカウンセリングサービスを活用することで、相談内容が評価や査定に影響しないと感じて気軽に専門家のサポートを受けられるようになります。
また、匿名で利用可能なオンラインカウンセリングや、社員専用の相談窓口を設置すると、相談に対する心理的ハードルを下げることが可能です。
さらに、労働安全衛生法で、事業者はストレスチェックを実施する旨が定められています。(※参考①)たとえば、年に1回以上のストレスチェックを全社員に行うことで、心理的な負担が高い社員を早期に発見でき、適切な対応を取ることができます。診断結果をもとに、燃え尽き症候群に前兆がみられる社員に対して専門家との面談を提供したり、業務の内容や量を調整したりすることで、社員の負荷を軽減することが可能です。
4. 休暇取得の推進
燃え尽き症候群の対策として、社員に適切な休暇取得の推進も効果的です。
燃え尽き症候群からの脱却とは、単に業務の負荷を下げたり仕事の手を抜いたりすればよいという単純なものではありません。今までの生活を振り返って過去の行為を思い出し自分自身を再発見して価値観を問い直すことが大切です。
有給休暇の取得率を向上させるためには、取得を奨励する社内文化を醸成することが必要になります。
また、リフレッシュ休暇の導入もおすすめです。勤続10年で2週間、勤続15年で3週間など一定期間のリフレッシュ休暇を義務化して、社員が心身を回復できる時間を確保する取り組みが効果的です。
さらに、休暇取得の進捗状況を管理職が定期的に確かめて、必要に応じて取得を促すことで休みを取りやすい環境にすることも大切です。
5. 教育・トレーニングの提供
社員一人ひとりが燃え尽き症候群のリスクを軽減し、ストレス耐性を高めるためには、教育やトレーニングの提供が欠かせません。
ストレスマネジメント研修では、ストレスに対する正しい対処法や視点を変えポジティブに捉える方法、ストレスを軽減するための対人コミュニケーションスキルなどについて学ぶことができます。また、社員が自分のキャリア目標や価値観に合致した役割を見つけられるように、キャリア開発プログラムやメンタリング制度を導入して、仕事に対するモチベーションや充実感を高めることも有効です。
管理職向けの研修では、自分自身のストレスの対処方法に加えて、チーム・メンバーにとっての良いストレスの設計の仕方や自身の仕事が円滑に進む方法についても学びます。これにより社員のメンタルヘルスを支援し、職場全体のストレス軽減が図れます。
6. 外部リソースの活用
燃え尽き症候群の対策には、外部リソースの活用が効果的です。
その中でも、人事顧問サービスの利用は、専門的な知識と経験を持つ外部の専門家から的確なアドバイスを得るための有力な手段です。
企業によっては、本業の業務に追われて人事やメンタルヘルスケアに十分なリソースを割けないことがあります。また、組織の内側にいると問題を客観視することが難しくなり、適切な改善策を見つけにくいこともあるでしょう。
外部の顧問は、第三者の視点から組織の課題を冷静かつ正確に分析することができます。さまざまな業界や企業での経験や豊富な知識をもとに、迅速かつ実効性の高い対策を講じることが可能です。
そのため、燃え尽き症候群など人事や総務に関する問題を素早く解決に導きたい場合には、外部リソースの活用がおすすめです。
人事支援なら顧問コンサルティングがおすすめ
職場の上司や同僚など身近な人物が燃え尽き症候群になるのは珍しいことではありません。
燃え尽き症候群になる原因は、業務量の多さや仕事の内容、人間関係などがあります。
しかし、その対策は、コミュニケーションや社内の体制強化をはじめ、ストレスマネジメント研修、休暇制度の充実など多岐にわたるため、自社の本業を行いながら対応を進めるのは簡単ではありません。
JOB HUB 顧問コンサルティングの人事支援サービスでは、さまざまな知見と経験、実績を持つ役員経験者などの専門家が約5,000名登録しています。燃え尽き症候群など、自社の状況を踏まえて課題を解決に導く専門家の候補を最短1週間でご提案します。
社外取締役の導入で職場の活性化や生産性向上を図りたい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶ 人事課題をプロで解決|JOB HUB顧問コンサルティング
※参考①:厚生労働省|労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル