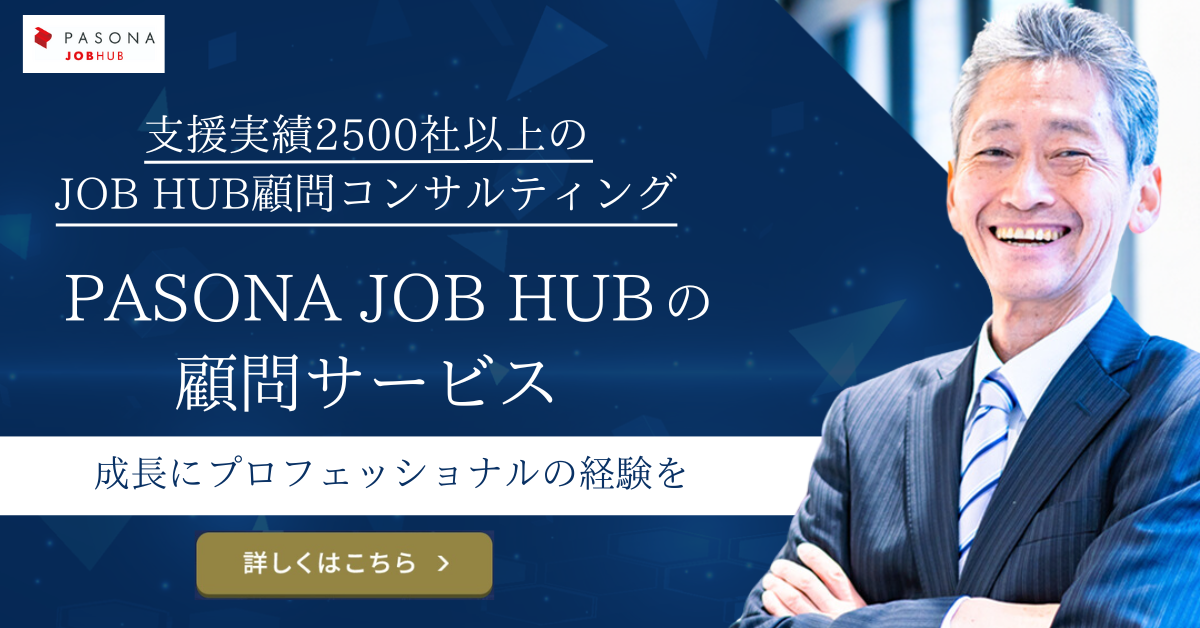人事制度とは、合理的な判断基準にもとづき、整合性のある人事管理を推進すべく用意されたシステムのことです。適切な人事制度は、組織の成長に欠かせません。とはいえ、「現行の人事制度が適切か判断できない」や「正しい人事制度の具体的な作成方法を知りたい」という声も多く聞かれます。
そこで当記事では、適切な人事制度の設計に向けて、具体的な手順・必要性・時代の変化に対応するポイントなどを解説します。人事制度の適切な設計について、理解を深めたいと考える企業担当者様は、ぜひ当記事をお役立てください。
目次
人事制度(設計)とは

人事制度とは、組織や上司の価値観に左右されず、人材配置や社内環境を整える仕組みのことです。人事制度が正しく機能すれば、組織も従業員も安心して過ごせます。
また人事評価制度設計とは、人事制度を「適切な仕組み」にすべく、具体的な計画や構築をすることです。
人事制度は一般的に、以下の3種類を指します。
- 等級制度…従業員のスキルや役割などに応じ、等級に分類する制度のこと。
(制度の例:職能等級制度、職務等級制度、役割等級制度)
- 評価制度…従業員の頑張りについて、目に見える形で評価する制度のこと。
(制度の例:年功序列、MBO、コンピテンシー、360度評価)
- 報酬制度…従業員の評価内容や貢献度合いによって、報酬を定める制度のこと。
(報酬の例:給与、ボーナス、退職金)
上述3つの制度が個別に存在するケースは稀であり、基本的には連動しています。
また人事制度が存在していても、「複雑すぎて理解できない」「単なる流れ作業になっている」など、制度が形骸化しているケースも見受けられます。人事制度の形骸化は、正しい結果を導き出せないのはもちろんのこと、従業員の不満を募らせ、モチベーション低下や離職などにつながる可能性もあるでしょう。
推奨される人事制度設計の手法・手順

人事制度は、各組織に応じた「正しい設計」ができてこそ、適切に機能します。不適切な内容で設計されると、望む結果とは「相反する未来」が訪れる可能性も否定できません。そのため、適切な内容で設計することが大切です。
ここでは、推奨される「人事制度設計の手法・手順」について解説します。
①現状把握とニーズ分析
人事制度は、企業理念や企業ビジョンといった「企業の実現したい目標」を踏まえ、目標達成に向けて設置される制度だといえます。たとえば、従業員のモチベーションダウンを改善したい場合には、従業員全体の士気を高められるような人事制度が好ましいでしょう。
実現したい目標を決めるには、現状の把握およびニーズ分析が不可欠です。現状を把握しニーズの分析をするには、現場の声を知ることが大切です。従業員の声を反映するには、要望や期待などをヒアリングすべく、「上司と部下との1on1」や「匿名で回答できるアンケート」等を実施すると良いでしょう。
また人事評価制度にもトレンドがあり、トレンドのなかでも「自社に適するもの」「自社に適さないもの」が存在します。そのため、外部環境の変遷をキャッチし、業界の動きを考察する姿勢も欠かせません。
②等級制度、評価制度、報酬制度を設計
現状把握とニーズ分析を実施し、人事制度で実現したい目標を設定できたら、目標達成に向けたプロセスに該当する部分を構築していきます。そこで重要となるのが、「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の設計です。
先述の通り、人事制度は「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3つで成り立っており、3つの制度は互いにリンクする関係です。すべてを正しく設定することで、適切な人事制度が設計できます。
~各制度における設計方法~
- 等級制度の設計…適切な等級数を定め、各等級の定義および内容を決める
- 評価制度の設計…等級制度と現状の差から評価結果を導けるよう、評価項目を決める
- 報酬制度の設計…等級制度や評価制度の内容を、適切に報酬に反映させる
上記のことから、人事制度を構築する際には、等級制度の設計から開始するとスムーズです。
③制度の導入・定着を目指す
人事制度を構築できたら、制度の導入を実施し、定着を目指します。
適切な人事制度を用意しても、従業員に詳細が周知されなければ、宝の持ち腐れになる可能性があるでしょう。人事制度の導入目的をはじめ、「等級のランクアップ基準」「評価項目の詳細」「等級制度・評価制度と報酬との関係」を認識してもらうと、人事制度が適切に機能しやすくなります。従業員が詳細を把握することで、人事制度に対する納得度も増すでしょう。
人事制度の導入および定着を目指す際には、以下のフローで進めます。
- 社員に人事制度を公表し、詳細な説明を実施する
- 定期的に法的な規制と照合する(常に法律は変化するため)
- 定着に向けたフォローアップ(改善点や従業員の声を確認)
また経営のトップから人事制度の必要性を説くことで、人事制度の定着が進みやすくなります。
令和時代における人事制度設計の必要性・重要性

人事制度を用意する際には、時代における人事制度設計の必要性・重要性も加味すると良いでしょう。取り巻く環境が激変する現代において、人事制度に盛り込む情報の新鮮さが、人事制度の良し悪しを左右する要素の1つになりえるからです。
実際に、先週に決まった内容が、翌週には通用しなくなるケースも見受けられます。人事制度においても、常に周囲への情報のアンテナを張りつつ、変化があれば即時に変更できるような姿勢が不可欠です。
人事制度に「時代のニーズや企業の立ち位置に応じた内容」を反映し、新たなスキルや知識の導入・適切な人材配置を実施することで、組織全体のパフォーマンスアップが期待できます。
また、「転職活動の日常化」や「柔軟な働き方を叫ぶ動きが加速」するなか、フレキシブルに対応できるような制度設計も必要でしょう。時代に即した柔軟性をもつ人事制度は、優秀な人材を惹きつける要素になり、結果としてハイパフォーマーの定着を促進することにもつながります。人事制度に対する柔軟な取り組みは、人材獲得への寄与をはじめ、企業イメージの向上も期待できます。ブランド力がアップすれば、さらなる取引拡大や、業績アップにもつながるでしょう。
人事制度の適切な設計は人材育成にも寄与

人事制度の適切な設計と人材育成は、組織の健全な成長を促進するうえで、深いつながりがあります。組織を動かすのは、その組織に所属する従業員たちです。そのため、人材を適切に管理する役目を担う人事制度は、組織の成長を促進するための根源だといえるでしょう。
また人材育成のステップは、人事制度と密接にリンクしています。人材育成をしたいと考える場合には、人事制度を整備することから開始すると良いでしょう。人事制度を整備すれば、人材育成の基盤が用意できるため、効率的な人材育成が実現できるようになります。
次項にて、人材制度の設計時に加味するべき「人材育成の要素」を解説します。
人材制度の設計時に加味するべき人材育成の要素
人材育成を効率的に行ないたい場合には、人事制度の設計時に「人材育成の要素」を加味することが大切です。ここでは、人材制度の設計時に加味するべき5つの要素について解説します。
OJT
OJT(On the Job Training)とは、新人や後輩社員などに対し、上司や先輩が実務を通じて、スキルや知識の習得を試みる教育です。とくに営業職のように「現場で経験を積み上げる必要のある仕事」は、OJTによる学びの機会が多いでしょう。また、講義やセミナーのような座学では補えない分野でも、OJTを活用するケースが見受けられます。
Off-JT
Off-JT(Off the Job Training)とは、業務環境から離れ、資格セミナーや語学研修などを通じて、スキルや知識の習得を試みる教育です。オフィス外で実施するケースもあれば、専門業者を社内に招いて短期講座を開催する事例も見受けられます。ほかにも、eラーニングやメンター制度の採択などが挙げられます。
オンボーディング
オンボーディングとは、新卒社員や中途社員といった「新たに組織に加わるメンバー」が、早く組織になじみ、活躍できるようにサポートするシステムです。
【オンボーディングの例】
- チームメンバーと一緒に食事をし、交流を深める
- 各自にメンターをつける
新たな組織に加わる際には、不明点や不安が生じるものです。オンボーディングを実施することで、懸念点を素早く取り除けるでしょう。
人事評価制度
人事評価制度とは、各自の頑張りを正当に評価し、モチベーションや業績の向上につなげる仕組みです。人事制度設計における「柱」の1つです。MBO・コンピテンシー・360度評価といった定番な内容から、従業員同士が報酬を贈るポイント性評価といった新たな内容まで存在します。評価スパンも、半年や四半期レベルのものから、週や日単位で評価できるリアルタイム評価など、バラエティーに富みます。
目標管理制度
目標管理制度(MBO)とは、前述の人事評価制度の一種です。目標管理制度の考え方は、人事制度を設計する際のヒントになります。目標管理制度は、従業員が自らの目標(※企業目標ともリンクする必要あり)を設定したうえで、目標達成に向けた適切なプロセスを用意するからです。人事制度の設計時に目標管理制度の原理を照らし合わせれば、適切な人事制度を構築しやすくなるでしょう。
上記で紹介した「5つの要素」を含む人事制度は、適切な内容につながるため、従業員のモチベーション向上や組織の競争力強化に寄与します。激動のビジネス環境であっても、変化に応じた内容を用意できることから、組織の成長を促進する効果も期待できるでしょう。
人事制度の適切な設計が難しい理由

人事制度の適切な設計を試みる際に、難しさを感じる人は多く見受けられます。多くの人
が「人事制度の設計が難しい」と感じ、目の前にハードルが立ちはだかる理由は、以下の通りです。
組織の多様性
組織には多様な形が存在するため、他社で成功した人事制度内容を、そのまま自社にあてはめても良い結果をうむとは限りません。
規模・存在する組織・文化など、さまざまな要素が絡み合うため、ニーズや要件によって人事制度内容が異なる背景も、設計の難しさを高めています。また同じ企業であっても、時が経過すれば、規模や組織内容も変化するでしょう。その時に適した人事制度を用意しなければいけないことも、人事制度の難易度を高めています。
従業員の多様性
同じチームに属する従業員であっても、一人ひとり、バックグラウンドや保有スキルは異なります。また、仕事に対するモチベーションやエンゲージメントの度合いも異なるでしょう。
従業員の多様性も意識しつつ、すべてのニーズや期待に応えうる人事制度の設計は、なかなか難しいものです。
企業によっては、「部署ごと」「働き方別(フルタイム出社・在宅ワーカー)」などに応じて、それぞれ人事制度を用意するケースも見受けられます。
情報の不確実性
従業員の能力やモチベーションについて、完璧に表現することは難しいでしょう。不確実な能力やモチベーション結果にもとづき、報酬や昇進などを判断することも、困難さを極めます。こうした「情報の不確実性」が、人事制度の設計における難解さを高めています。また、現段階の能力や気持ちも、時の経過に応じて変化するものです。
とはいえ、情報の不確実性を「可能な範囲で、正確に抽出する」ことは可能です。
人事制度の設計にコンサルタントの力を活用する方法も
人事制度の設計は複雑であり、設計のスキルや経験が求められます。そのため、知識の少ない企業担当者が独学で設計しても、適切な結果を導けない可能性が高いでしょう。不適切な結果は、従業員のモチベーションダウン・業績悪化・離職率を高めてしまうなど、期待とは相反する結果を招きがちです。
人事制度の適切な設計を実現したい場合には、設計や構築の業務を「外部コンサルタント」に委託する方法もアリだといえます。専門家に依頼することで、運用や将来的な見直しまで見据えた「適切な人事制度の作成」が期待できるでしょう。
人事に関する豊富な経験をもつプロ人材(顧問)が、研修プログラムの作成を支援
適切な人事制度の設計・構築・運用を実現するには、正しい知識や経験を有するプロに任せると安心です。「JOB HUB 顧問コンサルティング」では、各方面に精通した顧問の紹介が可能です。人事制度設計においても、経験豊富な顧問が「貴社の悩みや課題」を的確に把握したうえで、最適な解決内容を提案します。
たとえば、三井物産のモビリティ第一本部様では、グローバルなマネジメント人材の育成を目指すため、国際的な人事に長けている顧問を活用しました。担当顧問は、効果的かつ積極的な教育・研修プログラムを設計。実際にプログラムを適用した結果、ほんの数か月にもかかわらず、多くのメリットを実感できたとのことです。なかには、新たな教育プログラムの実施で不安を感じる従業員もいたものの、顧問が丁寧な説明や不安の払拭を試み、多くのメンバーから理解を求めることにも成功しました。
顧問は、ミッション内容にとどまらず、必要であれば、最適な提案の実施も惜しみません。社外のリソースを加えることで、新たな風を吹き込み、企業の持続的発展を促進する結果になったといえるでしょう。
人事制度について課題感を抱える企業様においても、パソナJOB HUB顧問コンサルティングが保有する豊富なデータベースから、課題解決につながる「経験豊富な顧問」を紹介いたします。
詳しい事例について知りたい場合には、以下の記事をご参照ください。
【 グローバル市場を勝ち抜く 】研修プログラムの見直しから見えてきた、人事のグランドデザイン
人事制度に関し、プロ人材(顧問)の活用をご検討の方へ
人事制度は専門的で難解な部分も多く、知識が乏しい状態で設計を行なうと、一定の壁が立ちはだかる可能性も高いでしょう。そのため、プロの活用を推奨します。
人事制度に関し、顧問の活用をご検討の場合には、顧問の紹介に強みをもつ人材サービス「JOB HUB顧問コンサルティング」がオススメです。人事制度の策定・設計をはじめ、企業様の成長に関するさまざまな課題に対し、プロの力を提供いたします。もちろん、自社に適したオリジナルの人事制度も作成が可能です。また、社内の「人事制度に関する理解」が不足する場合には、関係者を巻き込み、人事制度の重要性を理解してもらえるような施策も用意いたします。独自に保有する「豊富なデータベース」からの提案が可能なため、自社にピッタリの顧問が必ず見つかることでしょう。
人事制度に関してお悩みの企業様は、以下のページを、ぜひご参照ください。